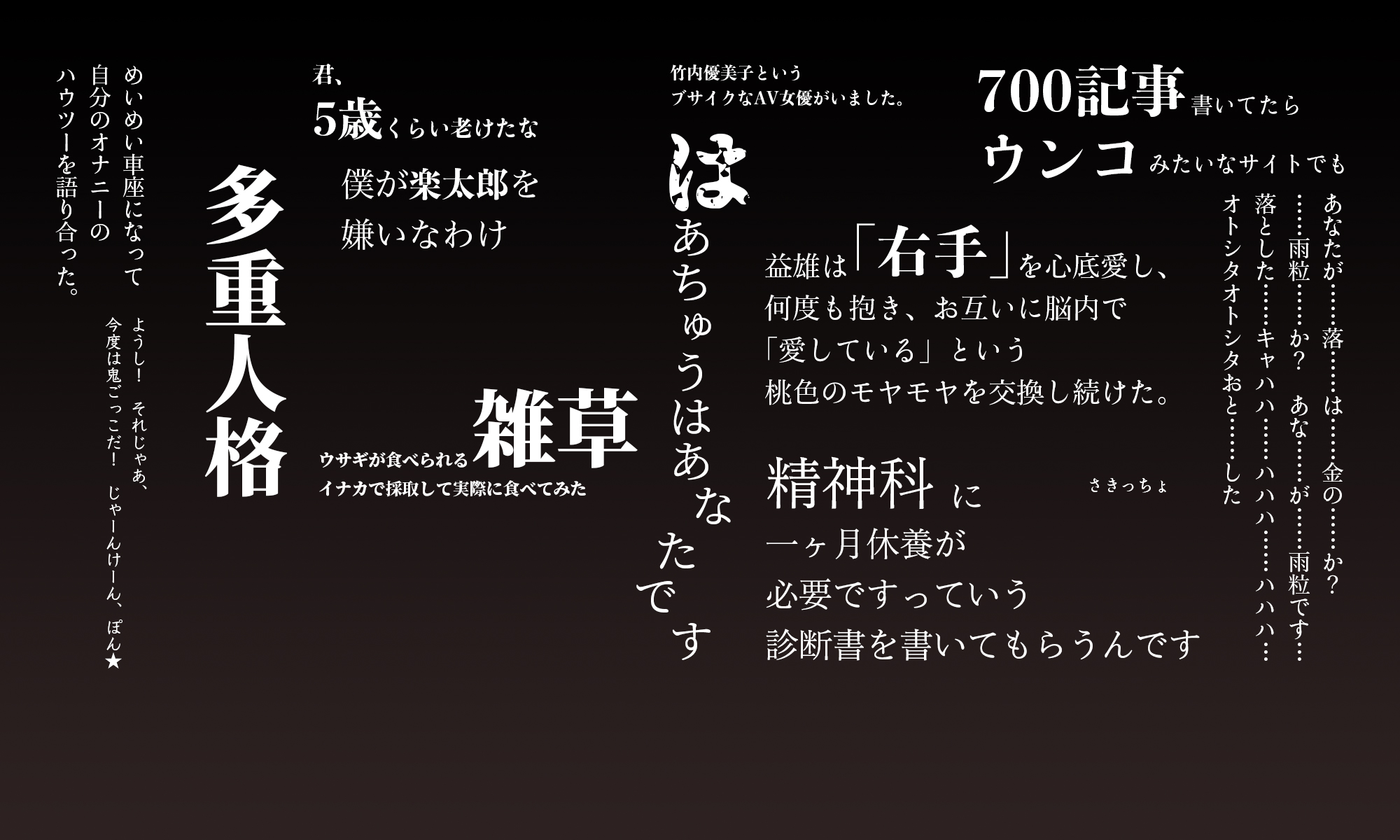(参考)
勧誘
-----------------------------------------------------------------–
初夏の暑苦しい空気と、クマゼミが「シャンシャンシャン」とどこか無考えに鳴いているBGMをバックに、木陰のベンチで涼しげに読書している僕がいます。優雅ですね。これぞ大学生ですね。しかし悲しいかな、僕の心の内は穏やかでない。途方もない孤独を抱えながら、何か強大な存在(留年)からただひたすら逃げている。ただこの存在(RYUNEN)は逃げたら逃げるだけ近づいてくるから不思議だ。それでも僕は怖くて逃げている。逃げる力を動力にひたすらに読書をしている。すごい読んだ。一週間で7冊ぐらい読んでる。すごい。いつだって逃げる力は強靭だ。ただ、その向き、ベクトルの角度をチラッとずらしてくれれば、と思うこともあるよ。ただそれがどうしたよ? と強がることで自我を保ってる。
「シネシネシネシネシネ」
クマゼミの鳴き声をこのように表現したのは江國香織だったか。江國さんもその作中でクマゼミをこう鳴かせたものだ。僕は一瞬そのことを思い出すと、なるほど、江國さんは鋭いなと感心し、僕もクマゼミの声に耳を澄ませた。シネシネシネシネ死ね死ね死ね死ね。わあ、とっても寂しい。
欝だ。おまけに寂しい。思えば今日は誰とも喋っていない。僕は想像する。自分は何かしらの影を抱える美青年で、大学の構内で、授業も受けず、ただ世界を冷めた視線で見、物憂げに読書をしている。「どいつもこいつも、なぜこんなに必死に生きているんだろう」などと冷たい炎(それはほとんど憎悪であった。生きているものに対する憎悪)を胸のうちに宿らせ、抜け殻のように生きている。そんな美青年に話しかけるは可憐な女性、「ねえ、同じ授業受けてるよね?」でも僕はその女性が誰であるか認識できないんだ。でも彼女と話しているうちに段々と分かってきて……中略……僕たちは、まるでフンワリとしたショートケーキをくずさないように、という形容がピッタリなほど、優しくお互いを包み愛し合った。僕はやっと自分の居場所を見つけたのだ。クズが!
要するにセックスじゃ! おら! セックスじゃ! そんなハルキ的展開がよおおお、落ちてこねっかなああ! なんつってなあ! 棚から牡丹餅ならぬ棚からセックス状態で、あんぐりと口を開けて待ってんだよ! 俺は! ずっと! 自分の演技力の限界を突き破る物憂げさで小説を! 読むんだ! 読んでたんだ!
したらまた生臭い臭いがすんだよな! また? またって言ったな俺今! そーだよ、何か嗅ぎ覚えのある臭いがすんなーって思ったら俺悟っちゃったわけ! これは俺が風呂に入らなかったときの臭いだ! ってな! 気づいたらジャージだし! ジャージで大学来てるし! めっちゃヒゲ生えてんし! もっじゃもじゃだし! あ? だからどうしたの!? その目。あんたたちのその目だよ! 俺が嫌うのは! いいか!? 僕は精神が薄弱してるんだ! その薄弱っぷりと言ったらカミーユとかキラとかいうレベルじゃない。僕は架空の一枚絵の悲劇の主人公より、真に悲劇らしい悲劇感を心に宿している! これが本当の悲劇の主人公や! しかるにお前らと来たらキラには「キラさまー!!! ギャー!!!」などと半狂乱で濡れるくせに、俺に投げかけるのはただただ侮蔑である。違いは何だ? 「違うことなんてない。誰もが平等で誰もが大切なんだよ。だから頑張って(はぁと」ぐちゃり。僕は心の中で斬馬刀を振り回すと、その圧倒的なGでもって、心の博愛主義者を壁に叩き付けミンチにする。うるせーよカスどもが! それじゃあ助けてくれよ! 俺が苦しいときに助けてくれよ! 助けてくれなかったじゃないか! あなたは助けてくれなかったじゃないか! もう殺す! あなたと戦っているとイライラする! やおら僕は心の刃(虎徹)を手に、縮地で一気に距離を縮めると、現実という怪物の白い喉元に白刃を押し当てる。現実ヲ殺スコト、スナワチボクガ死ヌコト! グッバイ現実! さようなら可哀想な僕……
「あのお、ちょっと時間いただいていいかナ?」
ブルブルと震え今にも発狂の爆弾が破裂しそうな僕の前に現れたんだ。マイエンジェル。天使は真夏の鋭い太陽を背に―それはあたかも後光のようだった―僕のベンチの横に手を差し出している。座ってもいいかナ? と聞いているのだ。大丈夫ですよ、と僕は物憂げに答える。すると彼女の表情は一瞬パアッと光り、「ありがとう」ともっとも人類の中で笑顔らしい笑顔を浮かべ、ふわりと僕の隣に身を落とす。シャンプーの匂いがサッと風になって僕の鼻を撫でていく。彼女はニコニコしながら僕に話しかける。
「今度ね、私達のサークルでゼミをやるんだけど。私は今そのゼミを紹介してまわってるの」
白いワンピースが彼女をより一層まぶしくさせる。風が吹くと彼女のスカァトがヒラヒラとまくれ、白い膝が見え隠れする。メガネの奥に潜む目は優しさに満ちている、ような気がした。
「へえ、なんて名前のサークルだい? 興味があるな」
僕のその返答を聞くとより一層彼女の表情は輝き、イキイキと希望に満ちていく。それと同時に何か、僕の心が掴まれたような、どこかへ行ってしまった様な心地がした。彼女は何かが書かれた紙を取り出すと、それを僕にみせながら話を続ける。紙には大きく「生きる」と書いてある。
「ほんと? うれしい! 私たち○○っていうサークルです。今度ね、ゼミをやるんだけど、そのゼミの内容っていうのはね……」
一瞬彼女は間を置くと、ここからが本番なの、とでも言いたげに謳うような調子で言葉を紡ぎ始める。その様子は誇らしげであり、そして親しげであり、愛に満ちているようでもある、気がした。
「今の世の中だとね、勉強しなくちゃならないでしょ? それで勉強して、就職して、仕事して仕事して……」
彼女は一変、表情を切実な様子に変化させる。その顔は、全てのものに同情しようと必死に努力している、未熟な女神を想像させた。美しい。未熟だからこその美しさ。
「それで自分の体に鞭打って、必死にがんばって……でもそれじゃあ人は倒れてしまう。力尽きてしまう。そんなときに必要なのは何だと思う?」
彼女は試すような視線で僕に問いを投げかけた。一瞬僕の眼下に広げられている紙を盗み見ると、大きく「生きる意味」と書かれているのが見える。生きる。生きる意味。イキル。
「生きる意味……じゃないかな?」
彼女はまたしても表情を輝かせると―それはもう、パアッという音が聴こえてきそうなほどだ―僕の肩に軽く手を当て、可愛いものを見たときの少女のように喜んだ。
「そうよ! 生きる意味よ! 人は生きる意味なくしては生き続けることができないの」
最後の言葉はまるで自分に言い聞かせるような調子だった。それを見て、ああ、彼女もまた闘っているんだなと思い、心を痛めた。
「それで、具体的には何をやるのかな? そのゼミでは」
僕は本当に興味を持って聞いたのだけれど、それを聞いた彼女は一瞬身構えた。顔がこわばっている。が、すぐにまた顔をもとに戻し、幾分緊張した調子で話を続ける。その緊張が僕にも伝わり、なぜか僕は罪悪感いっぱいになる。なぜそんな顔をするんだい?
「それは……難しいわね。一言で言うのは難しいんだけど……『生きる』というテーマで話し合うというか……」
僕は驚いた。彼女はとてつもなく大きなものと闘っている。僕らが就活だのテストだのちっぽけなものと闘っている傍らで、彼女は「生きる」という大きなテーマと闘っているのだった。それは聞いただけで辛さが伝わってくる重みだ。彼女が時折見せる影の表情の意味が、今、分かった気がする。
「『生きる』だって!? それは大きなテーマだね!」
僕は哀れむような調子で、空を仰ぎ、彼女を苦しめるその大きな存在を呪った。僕のような人間ならともかく、彼女のような可憐な存在にまで苦悩の触手を伸ばす「生」というものを恨んだ。恨んで、恨んで、それは自己嫌悪なのだと気づいた。彼女も苦しそうな顔をしている。僕の言いたいことが彼女にも伝わるのだろう。彼女は彼女の苦しみ、僕は僕の苦しみで苦しんでいる。しかし、こうして一緒にいればその苦しみも和らげることができるかもしれない。そう思って僕は彼女に微笑みかける。けれど彼女の表情は苦しいままだ。ああ、僕では役不足なのかい?
「た、確かに大きなテーマだわ。大きすぎるテーマかもしれない」
彼女の苦しみは僕より深く、深く、彼女の心をえぐっているようだ。僕には癒せない苦しみが彼女にはあるようだった。いや、誰にも癒せやしない。その苦しみを癒すのは自分しかいない。悲しい、過酷な事実だ。そしてそれは僕にも当てはまることだった。そうなんだ。
「で、具体的に何をやるんだい? 何かいつもやってる活動をあげてみてくれないか」
彼女は笑ってはいるけれど、目だけは苦しみを通り越して嫌悪の感情を呈している。今、まさに彼女は闘っているんだ。
「えっとね……あ! ○○っていう本があるのだけれど、あ! これは生協でも良い本だって紹介された本なんだけど、知らない?」
「知らない」
彼女は笑っている。しかしその笑顔の皮一枚へだてた内側では、憎悪とも嫌悪とも苦しみともつかぬ負の感情が渦巻いているのが見える。苦しんでいる。もちろん彼女が苦しんでいるのは「生きる」ことについてだ。僕はそれに何も手出しをすることができていない。
「まあ、その本はね。色々偉い人の言葉とかそういうのを集めた本なんだけど……それを教科書みたいな形にして、みんなで話し合いをするの」
一息にそれを言ってしまうと、彼女はどっとその顔に疲れを浮かべる。笑顔は既になく、僕と対等に話し合いをしているような、そんな表情をしている。そして僕は見た。見てしまった。彼女の表情に諦めという感情が浮かぶのを! ダメだ! 諦めちゃダメだ! 「生きる」を諦めちゃイケナイ!
「まあ、今知りたいのは、あなたが来てくれるか来てくれないかってことでね」
挑むような顔つきで僕を見上げる彼女。その顔は天使の面影を感じられないほど荒みきっていた。僕のせいだ……彼女は僕のせいで苦しみを思い出してしまった……! 僕は去らねばならない。これ以上彼女に苦しみを味合わせてはならない。
「ああ……そうっすねえ。そういうことはもっと生きるのに困ってそうな人に言ったほうがいいと思うよ。あ、まあ僕は生きるのに困ってそうだけどね。ははは。こら悲しい」
それを聞くと彼女は、「そうですか、ありがとうございました」と再び天使の笑顔を浮かべながら、そそくさと席を立った。そしてまた、近くに座っていた「生きるのに困ってそうな」男に声をかけはじめるのだった。僕はそれを見て悲しい気持ちになった。彼女は気づかない。そんなことをしても結局「生きる」苦しみから逃げられることはできないし、他人の「生きる」苦しみを取り除いてやることもできない。だってあなた自身が「生きる」苦しみを抱えているのだから。天使の姿なのに、あなたはボロボロだ。勿論、僕も。
彼女が去ってしまうと、空間がぽっかり穴を空けてしまった様で寂しくなった。読みかけの小説に目を落とし、小説の世界でたくさんの登場人物に囲まれていると、より一層自分が一人であることが認識できた。先の彼女はもういない。どうやらさっきの男には話を聞いてもらえなかったようだ。彼女もまた一人なのかもしれない。天使ですら一人。
僕は寂しさに満たされた心の部屋で、一人、虎徹をもって佇んでいる。虎徹の白刃が暗い(と思われる)部屋で妖しく光り、それはどす黒い芸術性をかもしている。美しく、寂しい。僕は正眼の構えでスラリと虎徹を構えると、何か大きなものに向かって切りかかる。ああああああああああああああああああ! 寂しさの咆哮、苦しみの咆哮、嫌悪の咆哮。白刃の切っ先が、空間とともに今にも何かを切り裂こうとしている。長い後ろ髪がたなびき、僕の顔の周囲に涙とも汗ともつかぬ、丸い小さな液体が爆ぜている。そのとき、部屋に一筋の明かりがスウッと横切り、部屋にある扉がゆっくりと開く。部屋の外には光が満ちている。
「すいませーん。ちょっとお時間よろしいですかー? 今、ゼミの紹介をしてるんですよー」
現実に戻り、声のするほうに顔を向けると、そこにはいやに細い男の人が一枚の紙を持って立っていた。紙には「生きる」と書かれていた。
そのとき僕は一人じゃないって思えたんだ。
↓ 人気ブログランキング。クリックで投票されます

たなばた☆公演告知 By Y平
↓最新記事はこの下にあります↓
「学生企画 たなばた☆公演」
愛知学生人形劇連盟APAS主催
7月8日 (日) 10:00開場 10:30開演
14:30終了 (途中1時間の昼休憩有り)
料金: 前売り500円 当日600円 小学生以下無料
僕の所属している人形劇サークルが出演する公演があります。
ヘアスタイル By Y平
前髪を切りすぎた、気が、する。いや、確実に切り過ぎている。鏡に映る我が顔を見ながら僕は先日行った美容室の、スカした美容師を思い出し憎憎しく思う。なんだこの髪形は、なんだこのブサイクは。
場面は先日の美容室に移る。僕が適当に美容師に注文を施すと、ヤツはクビを傾げながら言った。「前髪はも~うちょい、切ったほうがいんじゃないっすか?」だなんて、今にも語尾に「サーセンwww」とか付けちゃいそうな軽薄なトーンで言った。
そのトーン、言い方、顔の表情から伺える情報を読み取り、言葉に含まれる裏の意味を熟考すると、だいたい僕を馬鹿にしている感じで結論が下った。つまり「自分、髪のプロっすから。あんたの前髪論は間違ってますから。このダサ坊が」というようなニュアンスが言葉の節々に感ぜられたので、思わず、「やっぱそっすよね~。じゃあ切ってください」などと返答する。
しかしただ折れるにしても、負けたくない気持ちがあるので(一体誰に?)僕はさも、ヘアスタイルに関していくらか造詣があるようなフリをして答える。その手もありますね、みたいな論調で返答する。
美容師さんはその分かってる風の顔したダサ男に向かって、「っすよねー。(そうですよねの意)じゃあ切ってぁーす。(切ってきますの意)」などと軽い言葉を吐き散らかした。その軽々しい返事は美容室の壁のあちこちでこだまし、次第に空間を「どーせこいつ分かってねー」という裏の言霊で満たしにかかる。
さてチョキチョキ切り出す美容師さん。彼は軽やかに、そしてどこか恍惚な表情で、舞うように僕のヘアを切り刻んでいる。その間中、僕は伏し目がちで、終始鏡の下のほうにあるシールばかりを見ている。
なぜ鏡に写る自分を見ないのか。直視すればいいじゃない。鏡の中の自分を。一理ある。確かにそうだ。一方では、変身していく自身のヘアを見たい気持ちもある。しかし、見れない。それは変化していく自分を見て、「お、今の髪形、いいかも」というナルシスな表情を浮かべたくないし、見せたくない(当然ヤツに)という気持ちがあるからか。それとも逆に、変な風に切られてかっこ悪くなっていく自分を見たくないという、これまたナルシスな気持ちがあるからか。
とにかくそう言った負の感情を抱きつつ40分ぐらい目を伏せて大人しくしている。そしてヤツが器具を取ろうと後ろなどを向いているときに、「今だ」とばかりにチラリと鏡に映った自分を見やる。前髪が短い。
そんな短い前髪をあーでもないこーでもないと弄くるのは鋏を持った彼の仕事だ。右に流したり左に流したり。捻ってみたり、ファサファサと空気を含ませたり。しかし僕の前髪は彼の言うことを聞かず不恰好にクルクル回り、ただでさえブサイクな僕の顔に更なる負のアクセントを加える。チラリと鋏男の顔を見ると、難渋しているご様子。そら見たことか。
そのシザーマンは確かにプロであった。髪についてもよく分かってらっしゃると思う。しかし僕の髪は特殊である。ネコッ毛、クセっ毛、そういった枠に囚われない、孤高の天然パーマである。彼(天然パーマ)と付き合うには、彼を変えようとする行為ではなく、彼に従う行為が必須である。彼を生かす努力をせねばならない。長すぎれば無為にモジャモジャし不潔な印象を与えるし、短すぎればテレビ版(ただし1980年代中期)のジャイアンのような様相を呈す。

一センチニセンチの長短が彼のご機嫌を左右する。不潔かジャイアンか。彼と22年も付き合ってきた僕にしか分からない世界がそこにはある。昨日今日のシザーズに何が分かると言うのだ。
プロ様は渋い顔を浮かべながら、ひとしきり彼をねぶると、「まあこいつら(僕と彼のこと)のポテンシャルはこんなもんだわな」風の顔を浮かべて「おっつっした~(お疲れ様でしたの意)」と騒々しく叫び、僕を席から立たせた。鏡の中には微妙に前髪が短くなった僕が立っている。こんにちはジャイアン。
ジャイアンヘアで大学に登校すると――お~れはジャイアンなどと歌いだしたい気分だ――友人が「髪形変わったね」などと言ってきた。その言葉の裏にある真の意味を知りたくて、「変かな? 大丈夫これ大丈夫これ?」などと言いながら無意味にへりくだって見せる。僕の中では既に大丈夫ではない。答えは出ている。遠慮せず「かっこ悪い」と言ってくれよ。と、どんな罵詈雑言をも受けますというMの構えで、相手に向かって問いかける。「いや、別に。いいと思うよ」その返答を聞き、ワケが分からなくなる。
こんな記憶はないだろうか? 高校生ぐらいのとき。ワックスなどをゴテゴテに塗りたくり、髪を無意味に立たせ、無造作ヘアーでキメ! 鏡に映る自分をウットリと覗き込み、もしかして俺は絶世の色男じゃないかしらと勘違いをし、いざ登校。さあ、21世紀の在原業平ここに現ると言いたげな自信に満ちた顔をして、神々しい自身の御姿をば友人に御開帳。「お前、すっげえ寝癖だよ!?」「い、いやあ~。風が強くてサ」なんていうやり取り。
このように、主観と客観はおよそ違いが生じるのが世の常である。自分がいいと思っているものも、他人からしたら汚らわしい寝癖と解釈される場合が往々にしてある(特に中高生時代に)。それと逆のこともまたあり得るのではないか? つまり僕がかっこ悪いと思っているのも自分だけの話であって、他人からしたら何も変わらない、普段の僕なのである。いちいち前髪の長短を気にする僕を「んな、間違い探しじゃねーんだから……変わらねーよこのナルシストが!」と世間の目は見ているのではあるまいか。
すると僕はもともとジャイアンであったことになる。およそカッコいいとは思えないジャイアン属性で生まれてきたことになる。諦観の念が僕の自我に襲い掛かる。いや、かっこ悪いかっこ悪いとは思ってきましたよ。でも、僕、のび太くらいはあるかなーと思ってた。スネ夫の顔は人外だから追いとくとして、のび太レベルは堅いなーと思ってきたんだけどね。ジャイアンっすか。
がっくりするのも束の間、人は前を向いて歩いていかねばならない。ジャイアンだろうと勉三さんだろうと生きて行かねばならない。これこそ皆が好むポジティブな姿勢である。
僕は落胆する自分を必死に抑えながら、極めてポジティブに、快活に振舞う。「お前の髪形、ジャイアンだしwww」などと後ろ指差されれば、「なんだとのび太~! ギッタギタにしてやる~!」とおどける気概が僕にはある。そうしないといけない社会だ。なぜならそれが、自分の心に嘘をつき、ときには精神病にかかるまで追い詰められるにも関わらず、なお自分に嘘をつき、必死で弱い自分を奮い立たせ、他人に脅かされないがために、強くポジティブな自分を演出し、馬車馬のように働く社会人に求められる資質なのだから。
そんな思想のもと、快活なジャイアンを精一杯演じながら、彼女と会ったら、「生クリームが乗ったプリンのようだ」と揶揄され、ついに僕は人外の存在、スネ夫に等しき次元に上り詰め、「のび太のくせに生意気だぞ」と口をキツネ風にすぼめ、叫ぼうとしたが僕はプリンなので叫ぶことあたはず。ポジティブプリンは心の中で「やあ、僕プリンだよ。みんな食べてね」と精一杯おどけて見せたがプリンは思考しない。糞海のような社会の片隅でプリンはただそこにジッとしている。腐ってチリになるまでジッとしている。こんな社会は壊れるといい。
↓ 人気ブログランキング。クリックで投票されます