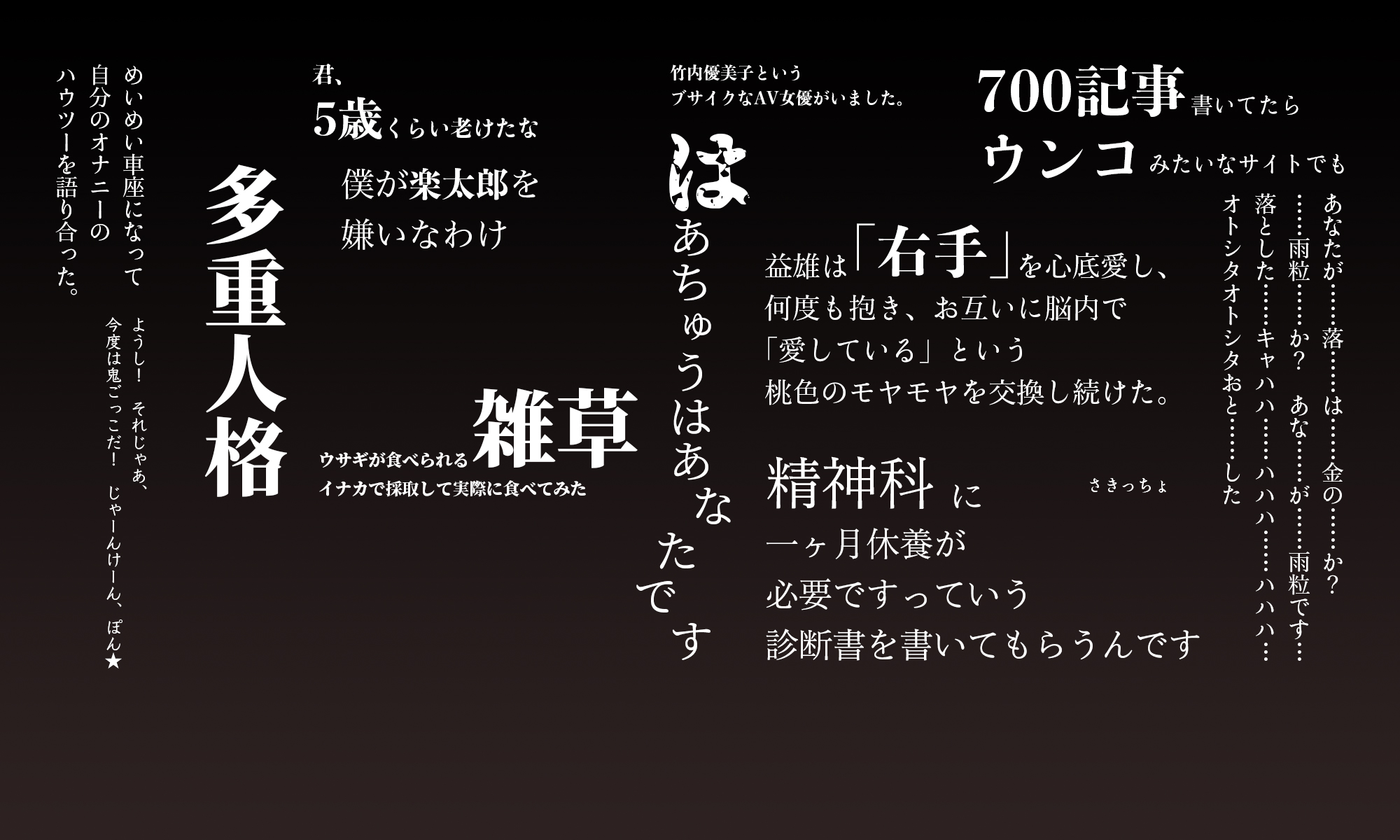2年前くらいに、この話を人形劇にしようとしてボツにされました。なにくそと思って今回、小説にして書いたのですが、正直半年近くも同じ作品に向き合っていると、もう自分では何がいいのか悪いのか分からなくなります。とりあえず、ものすごくつまらないなあって自分では思います。小説の体裁だけでも整ってればいいのですが……
原稿用紙換算で50枚程度と、素人の小説にしては読むに耐えない分量です。僕だったら素人の小説を50枚も読んでられっかと思います。ですが、ものすごくボランティア精神に溢れた方などに見て批評してもらいたいです。辛口めでいいと思います(死ね! とかでもいい。本当にそう思っている。何せ最後まで読んでもらえない可能性が高い)。誤字脱字の指摘もありがたいです。文の形式はブログで読みやすいよう変えてあります(改行の仕方とかカギカッコのルールとかが)。本当なら縦書きでキチンとした形式で読んでもらいたいのですが、今回は苦渋の選択ということで……よろしくおねがいします。
------------------------------------------------------------–
「金の斧銀の斧」
森の奥深く。鳥のさえずりや木々の葉がざわざわと擦れる音、風の爽やかな歌声以外には何も聴こえない、ふかーいふかい森の奥。森の一部分にぽっかりと、澄んだ空の色を映しこむ泉があった。泉には女神が住んでいる。
馬鹿正直なきこりが、泉に斧を落としてから既に久しい。
彼が泉に斧を落としたとき、女神が泉の底からすうっと現れ、「あなたの落としたのは、この金の斧ですか? それとも銀の斧ですか?」と聞いてきた。そこで、「いえいえ、私が落としたのは、そんな高価なものじゃなく、ただの斧です」と正直に答えると、自分の斧を返してもらえるだけでなく、金の斧や銀の斧までもらえるというお話。
いや、みなまで言う必要もなかった。その話は、もはや周知の事実であって、いまさらくだくだしく説明するほどのことでもない。子供でも知っているお話だ。
さて、重要なのはその後のことである。
本来ならば、この美談に何らかの教訓を見出さねばならないところだが、残念なことに狡賢い我々が、そんなところに重きをおくことのほうが不自然というものだ。たとえば、欲張りなきこりだって、最初こそ嘘をついて自分の斧を失ったが、それ以後は、どろどろした欲望をひた隠しにしながら、正直に落としたものを申告し、要領よく金銀を手に入れたと言う。
心の奥底で何を思っていようとも、とりあえず正直に落としたものを答えればいい。決して正直の美徳という概念は存在せず、良心とか体裁とかそういうのを度外視した我々の胸のうちに残ったものは、汚らしい欲望だけであった。
そういうわけで、うわさが噂を呼び、泉には金銀を得ようと大勢の欲にまみれた連中が集まることとなった。
私が初めて泉の森に訪れたとき。森の入り口には長蛇の列ができていた。そこには、上は高貴な服を着た貴族階級の人間。下には今にも裸にならんばかりのボロを纏った貧民。あらゆる階級の人間が集結しているようだった。
長く続く列を最後尾から前方へと目線で追っていく。果てしなく長い。遥か深い森の奥から列は伸びている。私は最後尾の荷車をひいた小太りの男に話しかけた。
「だいたい何時間待ちといったところだい?」
小太りは、私の容貌を値踏みするように眺めた後、ぱっと顔を明るくさせ、気さくに答えた。
「あんたここは初めて? こらあ何時間待ちなんてもんじゃないね。早くて三日というところだな」
幾分予想していたことだったが、私はそれを聞いて驚いた。いくら盛況だとはいえ、三日とは。遠方からやってきた手前、一応十分な食料や寝袋などは携帯してある。泊り込みでも問題はないが、骨の折れる話だ。
私は小太りの後ろにつくと、持ってきたカバンを下ろし、そこにどっかりと腰をかけた。すると小太りが楽しげに話しかけてきた。
「あんたは何を持ってきたんだい?」
私が、大きな皿を数枚持ってきたと答えると、彼は目を丸くした。
「あんた信じられないねえ。もっと大きなものを持ってこないと」
そう言って小太りは大いに笑う。私は彼に苦笑いを返しながら、ついでに彼にも何を持ってきたか尋ねた。すると小太りは、「こいつよ」といって自慢げに荷車に乗っているものをたたく。荷車には、ぼろぼろのタンスがくくりつけられていた。タンスとしては普通の大きさだが、これが金ともなると大ごとそうだ。
「こんぐらいの金が入れば、まあ三代は遊んで暮らせるってものだな」
そう言うと、小太りはいやらしい笑い声をあげた。私も少し笑った。一人でこれだけの量の金銀を運び出そうとしていることが滑稽だった。自分の求めているものが、どれほど重たいものかを分かっていないらしい。こういう輩ばかりなら、しばらくは大丈夫なのだが……
再度森の奥を眺めた。グネグネと、地面という地面に根を張った多くの木々は、巨大な触手をもった怪物のようで、そのどれもが手で抱きつけないほど幹が太く、よほど古い森であることが伺えた。その怪物樹たちの根元を、人が蟻のようにぞろぞろと列をなしているのが見える。列の先は森のさらに奥へと緑っぽくかすみ、先頭は遥か先のようだ。気持ちがひりつく。悠長に待っている場合ではない。一刻も早く金銀を得なければならない。私は思わず小太りに向かって言った。
「列なんか無視して、先に行っちまえないのかい。早いもん勝ちだろう?」
小太り、いや、私の周りで並んでいたすべての者が、その言動に一瞬警戒の色を呈した。まるでタブーか何かを言ってしまったような、いや、現にタブーであったのだろう。空気に緊張が走ったのが分かった。わずかな沈黙。その後、いかにもこういう場面にウンザリしているような、気だるく、しかし強い意志を持った風の口調で、小太りが語り始めた。
「あんた、それは無理な話さ。私たちは決めてるんだ。この泉はみんなに公平に使わせるべきだってね。そら最初のほうは、欲にまみれた輩が我先にと押しかけたらしいがね。そんなことになりゃあ、血なまぐさいことになるのは明らかだし、現にそうなっていた。おかしな話さ。せっかく神様がこのような素晴らしい泉をお作りになったのにね。そこで我々は、文明的な倫理にのっとって、その恩恵を公平に受けることを誓った」
まわりの人間も頷いている。私に侮蔑の視線を送ってくる者もいる。みんな小太りの小演説に同意しているようだ。私は皆の圧迫感にいらいらした。どいつもこいつも欲にまみれず秩序を守っているという自分たちに酔いしれている。その愚鈍な選択により、後々自分たちがどれほど不利益をこうむるかという想像力が、彼らには欠如しているようだ。
小太りは、なおもイライラのおさまらない私に、諭すように、否、半ば脅すようにして言った。
「お城の兵士も既に動いている。あんた、変なことをすりゃ、どうなるか分かったもんじゃないよ」
小太りに言われてよくよく周りを見てみると、なるほど。確かに、森のあちこちで屈強な兵士が目を尖らせ、歩哨のように周りに神経を配らせている。あせって行動を起こせば、たちまちのうちに殺されるというわけか。それも、秩序と正義の名の下に、公的に、冷酷に殺される。私のやろうとしていることが、限りある金銀を得るためには、きわめて自然な流れであることは、彼らには分からない。少し考えれば、正義とか秩序とか、そんなものが今必要ではないことが分かるものだ。しかし、彼らからすれば金銀は限りない、絶対的な価値として強く君臨している。現に金銀は泉から際限なく出てくるし、一見それが何よりもよいことのように思えるが、実は一番都合の悪いことだ。説明してやりたいという欲がちらちらと私の胸を掠めたが、そんなことをしても連中は理解しないし、よしんば理解したとしても、不利益にはなっても利益にはなりようもない。民衆とは、いざ、そのときになってみないと危機を感じないものなのだ。どうにもならない状況に、私は焦り、息が詰まった。そして、つくづくここの連中の愚鈍さを呪った。不本意ではあるが、大人しくするしか道はない。
「分かったよ」
私が諦め口調でそう言うと、小太りはじめ、周囲の人間は表情をゆるませ息をついた。急がなくても、もうしばらくは大丈夫。そう思い込むしかない。
その後数日。小太りや周りの人間と寝食をともにしながら、自分の順番が来るのを待った。私はその間に泉について色々なことを聞いた。
泉に落としていいものは一回につき一つだけであること。いっぺんにモノを投げ入れないこと。泉に投げ入れたものは必ず各自で持ち帰ること。女神様が疲れてしまうので、夜は泉にモノを投げ入れないこと。女神様に無礼を働かぬこと。小便や大便で列を抜けるときは警備兵に名乗り出ること。警備兵に逆らわないこと。騒ぎを起こせば当事者たちは列をぬけさせられる、または警備兵に斬り殺されること。厳密に取り決めが定められているようだった。あとは夜になると警備兵が兜や剣を泉に投げ入れているので、その現場は見ないようにすること。また、見かけても見て見ぬふりをすること。などなど。
周りの人間に、列のルールを教えてもらいながら、朝となく昼となくジッと並び続けた。そうこうしてる間に、いつの間にか森の入り口は後方に消え、三百六十度周りは巨大木たちのうっそうとした緑に包まれた。水を帯びた土の匂い。森がざわめく音と、列の人々の楽しげな声が空間を満たしている。
四日目の朝。遥か前方の木々が開け、光が漏れてくるのが見えた。泉だ。薄暗い森の中で、小太りと私は歓声をあげた。小太りなどは、あんまり騒ぎすぎたため、警備の兵に睨まれるほどであった。
さらに数時間の後。木々が目の前から急になくなり、サッと視界が広がった。直径百フィートほどの円形の泉が、透き通った青空と、対岸の森の水水しい緑をあざやかに水面に映している。のぞきこんだが最後、吸い込まれてしまわんばかりの清涼で澄んだ泉であった。あそこから女神が……うれしさのあまり叫びたくなるのを、警備兵の手前必死に抑えて、私は満面の笑みを浮かべた。
「あなたが落としたのは、この金の岩ですか? それとも、この銀の岩ですか?」
泉のほとりでは、白いローブを身に纏い、金髪の長い髪を優雅にたらした女性が、私がさんざ待ち焦がれていたフレーズを口にしている。あれが女神。信じられないことだが、彼女は人の丈ほどある巨大な金銀の岩を両手に持ち上げている。
さて、岩の意図的な落とし主である男は、女神を眼前にして泡を食っていた。この金銀が本当に自分のものになるとは未だ信じられぬといった感じの表情。金銀を得た後のあらゆる野心が、男の顔に浮かんでははじけ浮かんでははじけ。これから訪れるであろう幸福な想像によって混乱し、恍惚としていた。
それでも彼は、かろうじて心の隅にとどめることができた使命感に従い、動転しながらも、ゆっくりと正確に用意された答えを女神に伝えた。
「いいえ、私が落としたのは、ただの岩です」
その答えを聴いた女神はにっこりと微笑むと、
「あなたは正直者ですね。ご褒美に、この金の岩と、銀の岩を差し上げましょう」
と言った後、金銀の巨岩とただの岩を地面に落とした。小さな地響き。落とし主とその奴隷数人は、嬌声をあげながら岩に群がった。あーとか、うーとか訳の分からない感嘆の声を漏らしている。欲目におぼれ、理性をコントロールできぬようだった。女神はゆっくりと踵を返し、彼らを尻目に泉へと足を踏み入れ、そのまますうっと消えるように沈んでいった。
落とし主は、帰っていった女神に目もくれず、興奮した面持ちで奴隷達に命令をはじめた。テコや荷車などが手際よく用意されていく。身の丈ほどもある金銀など、果たして持っていけるのだろうか。
ふと泉の対岸を見ると、大小さまざまな金銀を運んでいる連中で、ごった返しているのが見えた。出口用の道が向こう側にあるらしい。そこに群がる輩のほとんどが、重すぎた自分の欲望に難儀し、うんうんとやっている。「泉に投げ入れたものは必ず各自で持ち帰ること」という取り決めを思い出し、私は苦笑した。
小太りの番がやってきた。彼は喜び勇んでタンスを荷台からひっぺがすと、勢いよく泉に投げ入れた。大きな水しぶきが上がり、波紋が泉全体にいきわたる。次第に泉の波紋が消えていくと、勿体つけたように泉の中央に女神が現れた。両手にはどこにそんな力があるのだろう、大きな金銀のタンス。まるでワイングラスか何かを手のひらに載せるかのように軽々持っている。彼女はするすると水の上を歩き、ほとりへと上がってきた。
「あなたが落としたのは、この金のタンスですか? それとも銀のタンスですか?」
そのとき、列の後方が突如ざわつき始める。森の奥から、妙な気配が。泉にいる全員がなにやらただならぬ様子を感じ色めきたつ。耳を澄ましてみると、大地の底から揺らしているような大勢の足音。森からは鳥たちのいっせいに逃げる鳴き声。獣の悲鳴。それに混じって、人々の暴力的な怒声やら、あるいは悲観的な叫び声が風に乗って流れてくる。森全体が、悪意のある侵入者がやってきたことを告げていた。人々の足音、怒鳴り声は次第に泉に近寄ってくる。
森の奥から、人々が大勢走って飛び出してきた。彼らは、そのまま泉に向かって突進してくる。どうやら列の後方に並んでいた連中らしい。列を抜かして強引に向かってくる彼らを前に、警備兵数人が、腰にさげていた剣をスラリと抜き、構えた。そして泉に殺到する者たちを次々と斬り捨てていく。が、斬っても斬っても、森の奥からはさらに人がわいてくる。
小太りのほうを見ると、こんな騒動の中でもちゃっかりと金と銀のタンスを手に入れていた。しかし、やはり重過ぎるのか、荷車に載せようとしてもタンスは微動だにしない。後ろから殺到してきた者たちは、金銀に難儀する小太りを確認すると、我先にと小太りのタンスに襲い掛かった。それに気づいた小太りが、野良犬でも追い払うように手をぶんぶん振り回して叫び、タンスに近づくものをぶん殴っていく。が、多勢に無勢。狂気の目をした一団に取り囲まれた小太りは、やたらめったらぶちのめされてしまった。比較的軽い、タンスの引き出しだけを全て奪われ、あとには骨みたいになった金銀のタンス、小太りの死体だけが残った。私はその光景を口を空けてただ眺めるしかなかった。
「静まれ! 静まらんかあ! これ以上列を無視するようなら全員なで斬りにしてやるぞ!」
警備兵の怒声もむなしく、相変わらず何十人もが泉に殺到し、勝手にモノを投げ入れる。そうでなければ、対岸の出口にたまっている、金銀の落とし主たちを片っ端から襲い、光るものだけを手にし逃げていく。
女神はそんな状況にも平然とし、泉にモノが落ちればマイペースに泉から出てきているようだ。女神の周囲には大勢の人々が群がり、エサを求める雛鳥のようにガヤガヤと騒ぎ立てている。彼女はこの騒がしい中、誰かの言った正直な言葉を聴き取ると、金銀のなにがしをボトリと落として去っていく。するとワッと人が群がり、争いが始まる。
気づけばあっちこっちで、人々が金銀を奪い合っているようだ。後方から来た連中はもちろん、さっきまで大人しく並んでいた者までも、いつのまにか金銀に目を狂わせていた。警備兵も民衆も関係ない。押さえつけられていた欲望が、激しい争いとなりはじけとんだ。
しかし妙だ。この列は「皆に分け与える」という美徳でもって動いていたはずである。遅かれ早かれ、並んでいさえすれば金銀を得られるというのが連中の拠り所ではなかったのか(もちろん、本来はそれではいけないのだが、みなは気づいていない)。更に言えば、後方から列を抜かしてやってきた連中は、おとなしいはずの民衆たちの顔であった。決して野盗の類が無理に泉に押し寄せたわけではなさそうだ。ではなぜ、彼らが列を抜かしてまで泉に走る必要があったのか。
私は地面に突っ伏してこの光景を眺めていた。金銀を得ようにも金を手にした瞬間、暴徒化した民衆に殺される恐れがあった。命を守るには動かないことが最良の選択に思えた。
「みな聴けえ!」
森の葉と大地が震え、時が一瞬にして凍りついた。森の奥から、警備兵とは比べ物にならないほどの大声が聴こえてきたのだった。後ろ、森のほうを振り返ると、鎧兜に武装した兵士達が、何十何百人とぞろぞろと森からわき出てくる。いつの間にか、泉とわれわれ一般人、警備兵を取り囲むようにして武装集団は円形に列を為し、泉のそばで固まっている我々を睨みつける。彼らの人数は警備兵のそれより遥かに多い。
ちょうど私の正面から大将らしい男がのしのしと肩をいからせ歩いてきた。再び耳をどっしりとぶちのめすような大声で言った。
「我らはそなたらの隣国のQ国である。金銀を出だす泉があると聞いて、それを召し取りに来た次第だ。持っているものをその場に置き、速やかに我らに投降せよ。逃げ出したり、抵抗すれば容赦はしない」
男の声をうけて、泉にいる全員が硬直した。みな一様に大将のほうを口を開けて眺めている。
列の後ろのやつらが、突然泉に殺到したのはこういうわけだったのか。Q国が攻めてきたと知った後方の民衆は、彼らに占領される前に、さっさと金銀だけを持ってとんずらをする算段だったのだろう。しかし取り囲まれてしまった今となっては、それも叶わぬ夢だ。
静寂。先ほどまで争っていた人々も、ボーっと突っ立ったまま微動だにしない。各々、自分が置かれている状況を頭の中で必死に整理しようとしている顔だ。
時が止まったままさらに五秒が経った。そのとき、警備兵の男が一人、隣にいた男を斬り殺した。トマトをぶっ潰したような鮮血が警備兵の顔を黒々と染める。彼は男の持っていた金の鍋をひっつかむと、なにやら訳の分からない声でわめきながら、森に向かって一目散に駆け出した。
その声を合図にし、皆がみな、泣き声とも叫び声ともつかぬ声をあげながら、手近の金銀を抱え走り出した。森の中に逃げ込む気である。大勢の人の声と足音が、戦場のように泉をふるわす。
といっても、四方をQ国の兵士に囲まれた我々に、金銀を持ち逃げすることなどできやしなかった。森に達する前にQ国の兵士によって造作もなく斬り捨てられていく。泉のまわりには、民衆と警備兵の死体、金銀が次々と転がっていく。私はその光景を震えながら眺めていた。腰が抜けているのか、まったく足が言うことを利かない。まわりにも、恐怖のあまり動けない人間が数人いる。しかし、大半の民衆は金銀のために命をかけて、Q国の兵士に向かっていく。斬られて命を失いゆく人々は、金銀を手にしながらここで倒れてしまう運命を呪い、くやしそうに呻いていた。何が彼らにそこまでさせるのか。金銀とは、かくも人を狂わせる品物なのか。私には分からない。極めて作業的に人を殺していくQ国の者も、金銀を抱え、簡単に剣に向かって突進していく民衆も、全てが架空の物語のように現実の色を帯びていないと感じる。
数分にわたる虐殺。Q国のものが、死にきれずあちこちで呻いている民衆に、最後にずぶりと胸だか首だかに剣を突き立てる作業が終了すると、泉に再び静寂が訪れ、もはやQ国の者以外、動くものはいなくなった。Q国の将が、へたりと座り込む私の横を、ゆうゆうと通り過ぎていく。泉全体を見渡し「馬鹿な奴らだ」と吐き捨てるように将はつぶやく。
彼は泉に近づいていった。泉のはしにはキョトンとした表情で佇む女神。腕には誰か泉に落ちたのだろう、金の中年オヤジと銀の中年オヤジを抱えている。
女神は、自分に近づいてくる将を確認すると、ニッコリとして話し始めた。
「あなたが落としたのは、この金の中年ですか? それとも銀の中年ですか?」
Q国の将は、きらびやかな中年を一瞥すると、冷酷な笑みを浮かべて答えた。
「そうだ。私が落としたのは金の中年だ。早くそいつをよこせ」
その答えを聞いた女神は、悲しそうな顔をしてお決まりの批難をしたあと、そのまま泉の中へと帰っていった。「傑作だ」Q国の将はおおいに笑った。欲望と残忍さが入り混じった奇妙な笑い顔である。金銀じゃないほうの中年はどうなってしまうのだろうか。私は万に一つも金銀を持って無事に森を出られることはないだろうと感じた。それどころか、先ほどの虐殺の恐怖も相まって、命があるだけで十分な気持ちであった。フッと力が抜け、金銀への執着がしゅうしゅうと、音を立てて萎んでいくのが分かる。
Q国の将は、女神が泉に消えたのを確認すると、自分の剣を泉に投げ込んだ。
そこで私は見た。いや、既に私は見ていたのだが、金銀の色眼鏡をはずした、クリアーな視界で再びそれを見た。
女神が泉の中央から、透明な水をゆっくりと上品に突き破り、水上に浮かび上がってきた。泉の中央に、直立不動で佇む女神。女神が纏っている、真っ白なローブの肩から、きれいな水がローブのしわを、液体になった銀が流れるかの如く滑り、足元に滴り落ちる。
彼女がゆっくりと水上を歩くと、肩口にかかった金色の髪がやわらかになびき、髪全体が生きているかのよう。肌は透き通るように白く、目鼻立ちは整い、見てるこちらがとろけてしまいそうな、柔らかな微笑が私の心をぐらぐらと揺らす。泉に反射した陽光は女神の頬を、優しい水の光でもってゆらゆらと照らしていた。
美しい泉に立つ美しい女神。最高のステージと、最高の女優を持ってすれば、そこらへんに落ちている、精巧な金細工たちもたちまち霞んでしまう。それは、人間の欲望を度外視した、もっと心の清廉な部分に訴えかける何かがあった。私は先ほどまで金銀に執着していた自分を恥じた
女神は泉からほとりへと、その美しい裸足を踏み出し、柔和な笑みを浮かべながら大将に話しかけた。手には金の剣と銀の剣を持っている。
「あなたが落としたのはこの金の剣ですか? それとも銀の剣ですか?」。
その日以来、私の胸には女神の美しい姿が焼きつけられ、一日として思い出さない日はなかった。
いったん女神の泉がQ国の統治下に入ってまもなく、泉をめぐって国と国同士での大規模な戦争が勃発した。人々は女神が作り出す無尽蔵の金銀を得る権利を夢想し、手段を問わず争いあい、多くの人々が死んだおかげで多くもの憎しみと不幸が世の中に蔓延した。
当然の如く、私が泉に近寄ることは許されなかった。泉は国にとって大切な利権であり、一般人である私が利用する権利があるはずもなかった。私が欲しいのは金でもなく銀でもなく、女神である。しかし、彼らが守っているものもまた女神なのだ。正確には、女神の出す金銀を守っていたのだが。
ただ私は希望を捨ててはいなかった。予測では、必ず再び女神の泉が解放されるときが来るはずであった。町々にあふれる、私はきらびやかな金銀細工を横目に、そのときが訪れるのを辛抱強く待ったのだった。
Q国が泉を統治し始めてから一ヶ月あまり。ようやく世間は私の思惑通りの展開になってくる。愚かなQ国の王が、大量の金銀を求め、その多くを市場に流出させたため、金銀が極端な値崩れを起こしたのだった
当たり前のことだが、金銀は少ないからこそ価値があるのだ。国中の誰もが金銀を持てるような世界になれば、それはもはや人々の望む金銀ではない。どんどん金銀の値段は下がり、今や、パン一斤買うのに、金貨を五万枚財布から出さねばならなくなった。同じだけあったはずの食料は、不況のあおりを受け、どこへどう流れたのか。一般の民衆には一切手の届かぬ存在となっていく。金は以前よりあるはずなのに、それ以上の金を出さなければ、何も買うことができない。民衆は混乱し、すさみ、やがて飢え始める。
私が以前住んでいた、白い石作りの家が立ち並び、多数の市が立つような大きな街。その街にも金銀の調度品……否、金銀という名のゴミくずが溢れた。
一見、街は裕福そうに輝いている。しかし、金銀でもって一際明るくなった街の公道では、餓死者が倒れ、誰も片付けないまま腐っていく。その死肉を貪るハエたちが往来を行きし、ブンブンと騒がしい。妙な腫れ物を顔や手足にこさえ、死んだように歩く女。金の装飾品を体中に身につけ、細い体をぐったりと商店の壁にもたせかけ、口をあけながら物欲しそうに往来を眺める男。体中にブツブツができて、青黒くなった赤ん坊の死体を抱き、突っ立っている少女。その少女の手にはしっかりと金の石が握られているが、少女とてその金の石が何の役にも立たないことを知っている。
誰もが死んでいるか、死んだようになってるかで、活発に動いているのはハエとカラスと、一部の支配階級のみである。かつて人々が女神の泉で夢見たであろう豪勢な生活の影も形もない。人々は、金よりもその日生き延びるための食料を求め、餓鬼のように街、あるいは草原、森をさまようしかなかった。
金銀が値崩れを起こさぬうちに、さっさと他の代替的財産――農地だとか、牛や羊などの家畜――と金銀とを取替え、安定した生活を得ようという私の計画は見事崩れた。そればかりか、インフレの煽りを受けて財産を失った私もまた、森をさ迷い歩いては、猟師でもないのに狩りをし、木の実を食べ空腹を満たす、その日限りの生活を強要された。
世情も不安、私自身の生活も安定しない。世の中に平和と幸福など訪れぬムードが漂う中、しかし私は喜びに満ちていた。金銀がゴミとなった今、私と女神を阻むものは誰一人といないのだと思うと、空腹も気にならなかった。
Q国の一件があってから三月後。私は再び泉の森を訪れた。月の真ん丸な、少し冷え込む夜だった。巨大樹のグネグネの根っこを縫うようにして森を進むと、以前四日かかったのがウソみたいに、あっさり泉のほとりに出てしまった。ちょっと前まで厳重な警備がなされていた泉も、今は子供に飽きられたオモチャのように、ぽつねんと、静かに月を映していた。
泉のほとりには大量のゴミ――といっても全て金銀だが――がゴロゴロと置き捨てられたままになっていた。今となっては荒れ果てた地、という印象を受けるのが皮肉だ。しかし、泉そのものは鏡面のように澄み渡り、三ヶ月前となんら変わらぬように見える。
私はゆっくりと泉に近づき、近くにあった小石を拾い上げた。そして、泉の中で息をひそめているであろう女神に、手渡すかの如くそうっと小石を沈めてみた。しばしの静寂。果たして女神はまだこの泉にいるのだろうか。私は女神と再び出逢える事を信じ、じっと待った。
小石が作った小さなさざ波が、霞むようにして泉に溶け込むと、目の前の水面から、柔らかな光が漏れてきた。ゆっくりと、女神が水面に浮かび上がり、水面上に直立に立つ。ニコっとかすかに笑うと、金銀の小石を手に陸地に上がってくる。
微笑を浮かべながら私の前に立つ女神。水から出てきたばかりだというのに、その白いローブはまったく濡れておらず、干したてのシーツのように、フンワリと夜風になびいている。柔らかな微笑み、肩口をさらさらと撫でている金色の髪。存在そのものが暖かく、柔らかな印象。見ているだけで心が洗われ、たまらなく愛おしく、私は女神を抱きしめたいという衝動を抑えるのに必死だった。
「あなたが落としたのは、金の小石ですか? それとも、この銀の小石ですか?」
女神は例の如く、透き通った声でお決まりの文句を紡ぎだした。三ヶ月前であれば、私はこの言葉に欲をむき出しにして応えるところだったが、今は別の静かな感情によって、私の心は穏やかに凪いでいた。
「落としたものは、どうだっていいのです。それよりも、あなたともっとお話がしたい」
私はなるべく控えめに、紳士に、それでいて言葉の奥底に熱を残して女神に話しかけた。
女神は、おそらく初めて聞く種類であろう反応を前にし、明らかにその美しい顔に驚きの色を表した。そして、幾分困ったような、泣き出しそうな表情で私をジッと見返し、静かに口を開いた。
「あなたが落としたのは、金の小石ですか? それとも、この銀の小石ですか?」
悲しそうに言葉を繰り返す女神を見て、私の胸がキュウッと音を立てる。
「あなたはどうしてこんなことをなさっているのですか? 何の因果でこんな……」
「あなたが落としたのは、金の小石ですか? それとも、この銀の小石ですか?」
女神は私を前にして、もはや何の価値もない呪文を唱え続ける。
「人間の道徳心を試すためですか? ただ単に金銀を人に与えたいだけ? それとも――」
「あなたが落としたのは、金の小石ですか? それとも、この銀の小石ですか?」
目に涙をため、声を震わせてもなお、女神は女神としてのマニュアルを遵守していた。
道徳心。そういったものがまだ世の中にあるのなら、よかったのかもしれない。いや、金銀に群がる欲望でさえ、あるにはこしたことはなかった。だが、その両方ともが、女神の前から消え去ってしまった今。世間での女神の存在価値は欠片もなくなってしまったのである。
私はてっきり、彼女はその事実を悲壮的にもならず、周りの世俗一切をわれ関せずとして受け止められる、神のような精神構造を持っているものと考えていた。
「あなたが落としたのは、金の小石ですか? それとも、この銀の小石ですか?」
しかし、現実の女神は今や涙をポロポロと零しながら、私に金銀を差し向けている。その姿は、もはや神のそれではなく、悲劇の因習に縛られた、一人の女性であった。誰からも意に介されなくなり、自分はなんのために存在するのだろうと考える毎日。平気であったはずがない。
マニュアルをかたくなに守る彼女だったが、目だけは自由を渇望しているように見えた。
女神は、私が押し黙っているのを見ると、しゅんと残念そうな顔をして踵を返し、ゆっくりと泉に戻っていった。残念そうな顔が、私が問いかけに答えなかったことによる失望なのか、自由への足かせを解いてくれなかった私に対する失望なのか、もはや言うまでもなかった。泉に映っていた月はどこかへと消え去り、私の視界には闇に浮かぶ泉だけが残った。
私は薄い毛布にくるまり、巨大樹の根っこで芋虫のようにして横たわった。女神に感情や人格がある。それを悟った私は、泉のそばにキャンプを構えた。こうなれば気長にいくのみだ。どうやったら彼女をこの忌まわしい呪いから救えるか、ひたすら考える。
夜風は冷たく、毛布の隙間から入ってくる風がサッと首筋をなで、思わず毛布の中で縮こまる。泉の中は、もっと冷たいのだろうか。次第に私の意識は闇に溶け込んでいった。
巨大樹の葉と葉の隙間から、弱弱しい陽の光が差し込み。私の顔をチラチラと照らしていた。朝だ。毛布から出ようよとする、体が冷え切っていてうまく動かせない。這い出るようにして出ると、冷たい空気が手足を刺す。毛布の上には、巨大樹の落葉がパラパラと積もっており、毛布の片側を持ち、ゆっくりと上に持ち上げると、バサアッと葉が落ちた。泉には白い霧が立ち込めている。吐く息はもやっと白い。明日からは焚き火をして寝たほうがよさそうだ。
泉の周りを見回してみると、泉の反対側に人影が見える。たちこめた霧のせいで、よくは見えないが、どうやら女性のようだ。私は泉をぐるりと回って、その人影に近づいた。
女神だった。彼女は、朝もはよからお勤めらしい。金の木の実と銀の木の実を手に乗せ、誰かに話しかけている。……誰に?
「あなたが落としたのは、金の木の実ですか? それとも、この銀の木の実ですか?」
女神の問いかけに答えるものは誰もいない。それもそのはず、女神が話しかけているのは、泉の周りを取り巻く巨大樹たちだった。風で木の実が落ちたのだろう。彼女は律儀にルールを遵守し、返事もしない巨大樹相手に、仕事をこなすのだった。
私が目を丸くしてその光景を見ていると、女神がコチラにふっと顔をやった。一瞬の間。女神の表情はぐにゃあと幾通りにも変化し、泣き出しそうな、笑い出しそうな顔で私を見返すと、しまいにうつむいてしまった。その間も、口だけは自動的に例の呪文を唱え続けている。見られてはいけないものを見せてしまった恥じらい。女神は声だけは明るく、しかし顔をタコのように赤くしてジッと下を向いている。私のほうを見まい見まいとしているようだった。
人が落としたものである必要はない。女神はモノが落ちれば落とし主が誰であろうと、出てこなければならないらしい。落とし主のいない落し物を抱えては泉から出、うわ言の様に言葉を発する女神。胸の辺りがスウスウし、私は女神から目をそらす。
しばらくすると、女神はやっと解放されたとでも言いたげな、疲れた表情で泉に入っていった。彼女は泉に入りきる直前、顔だけ出した状態で私のほうをチラリと見た。私の口から自然に言葉が滑り出す。
「おはよう。今のは……見なかったことにするよ。また後で会いましょう」
女神は顔を赤らめ、それでも少しだけ微笑んでから泉に沈んでいった。
巨大樹が落とした枝を拾い集め、焚き火をする。森のあちこちで生えていた、キノコや野草などをとり、泉の水でゴシゴシと洗って串に刺して軽くあぶる。ころあいを見計らって塩をふりかけた。キノコの香ばしい匂いが漂う。そうこうしている間に、太陽が体を温めてくれるほどには仕事をするようになってきた。心地よい昼。白く冷たい霧が消え、森に緑っぽいつややきが戻ってくる。
串に刺さったキノコに噛み付いていると、陽の暖かさも相まって、目はパッチリ開き、胃袋に入ってくる食べ物が、体の内側からポッポとエネルギーを送ってくるような気がする。周りを見回しても誰もいない。私は思わず飛び跳ねたくなる。
何はともあれ、女神と再び会うことができた。やや一方的だが、コミュニケーションもとれそうだ。私は持っていた串を投げるようにして焚き火に突っ込むと、すっくと立ち上がり、さあこれからどうするか。パッパとズボンをはたき、キッと泉をにらみつけた。
すっかり肌寒さの消えた日中。とりあえず小石を泉に投げ込んだ。勿体つけたように女神が泉から出てくると、私は軽く手をあげる。彼女も小さく会釈をした。しかし表情は硬く、目がひらひらと泳いでいる。私と話をするのが気がひけるらしい。しかし、それでも女神のマニュアルを破るわけにはいけないらしく、オズオズト私の前まで歩いてきた。そして、金銀の小石をこちらに見せるように掲げながら、例の文言を呟いてきた。私はひとまず質問は無視して、女神に話しかけてみる。
「ええと、こんにちは」
女神は口元を少し緩めた。
「いつも木に向かってああしてるんですか?」
ハッと、思い出したように顔を赤くした女神は顔を伏せる。私は軽く笑い、続ける。
「いや、いいんですよ。なんだか面白かったから」
彼女は更に頭を垂れ、「あなたが落としたのは……」と囁く。
「ちがいます。馬鹿にしてるわけじゃなくて」
女神はフッと顔をあげてジッとこちらを見つめた。私を足の先から頭のてっぺんまで舐めるようにして眺めている。手に汗がにじむのが分かる。口が渇き、耳があつい。金色の髪と、白いローブとのコントラストが眩しい。頭が空っぽになって二の句がつげない。
女神は固まっている私を見て、不思議そうな顔をしている。私は少しだけ深呼吸をし、女神の目をジッと見つめた。その間も女神は、「あなたが落としたのは……」と何度も何度も繰り返している。私はそのセリフの切れ目を狙って、女神に訴えかけた。
「単刀直入に言います。私はあなたのことが好きになってしまいました。どうか一緒に来てくれませんか?」
彼女は、あっけにとられた顔で固まった。私の言葉を頭の中で必死に整理しようとしているようだ。無理もない。こんなことを言う者など、今までいなかったに違いない。それでも私はマゴマゴする女神を見て、少し不安になった。
「すいません……性急すぎましたね」
ハハハと笑う私を見て、女神も少しだけ微笑んだ。そして私の顔をジッと見つめると、諭すような優しい目をしながら、ゆっくりと首を横に振った。
「やはり泉からは出られませんか?」
女神はコクリとうなずくと、またお決まりのセリフを続け始めた。
それから数日間、私は泉に滞在し、日に何度か女神を呼び出しては話をした。話といっても、女神は呪いか何かのように、決められた言葉以外は話すことができなかったが、私の話にうなずいたり、表情を変えることでコミュニケーションを取ろうとしてくれる。うまい具合に質問していけば、女神の考えていることは、だいたい理解することができた。
色々な話をした。とりわけ私が故郷の話をすると、彼女はとても喜んだ。故郷の風習、人々、私がどういう風に育ってきたか。そんな話を目を細めながら彼女は聴いていた。時折、なつかしそうにうなずく彼女を見て、「あなたの故郷は?」と聞くと、目をつぶり、ゆっくりと首を横に振った。自分の話になると、女神は禁忌に触れまいとするかのように固く感情を閉ざした。そういうときは、もう聞いてくれるなと言いたげな顔をする。
親しくなると、女神は子供のように多くの話をせがんだ。泉に永きに渡って拘束されてきた彼女にとって、どんな話でも新鮮に映るようだ。毎日私は、話を3つ4つ考え、さあこの中からどの話が聴きたい? と尋ねることが日課になってきた。そして、大抵の場合、女神は「全部聴きたい」と目をキラキラさせる。日が昇り、沈むまで私は話をする。ちょっとしたことでも、ウンウンと関心を持った目で聴いてくれる彼女を見て、私は心底愛おしいと思うと同時に、彼女のことを少しでもいいから知りたいと思うのだ。
冬の足音はすぐそこまで近づいきていた。朝夕の冷え込みは私の気力を徹底的に削り取った。加えて、数日前までは生えていたキノコや野草の類が目に見えて減っていた。食料を求め森をさまよい、絶望にくれる。そんなとき、私は小石を泉に投げ込んだ。
女神を泉から連れ出すことこそ叶わなかったが、私は幸せだった。彼女は私が呼ぶと喜んでくれるし、取り留めのない話だろうと何でも楽しそうに聴いてくれた。不況により先の見えなくなった世の中。生活は苦しい上、のち数週、本格的に冬がやってくれば、簡単に飢え死にしてしまうことだろう。しかし、こうして女神という拠り所のある今なら、そんな運命でさえ受け止められる自分がいた。泉に縛られていたって構わない。女神と過ごせる幸せを、終わりのときが来るまで緩やかに味わいたい。
しかし、それがどれだけ独りよがりだったかを、思い知らされる事件が起きた。
ある朝、大粒の雨が降っていた。巨大樹のかげで寝ていた私は、葉っぱによって受け止め切れなかった雨粒が、ボタボタと毛布を濡らしているのに気がつき、目を覚ました。体は芯から冷え、手足が冷たすぎて痛む。関節がこわばり、体を動かす気がしない。私はじっとりと濡れた毛布の中で縮こまり、ひたすらに震えた。毛布のかげから目だけを少しのぞかせ、ぼんやりと泉を見る。雨の降りしきる中、泉では、雨粒によってできた無数の白い水しぶきが生き物のように躍っていた。
滝のように降りしきる雨。泉の対岸は白く霞み、視界がひどく悪い。バババババと雨粒が激しく地面を叩きつける音のみが空間を支配し、頭がボンヤリとかすみがかったようだ。
そのとき。重い頭のまま、地面にはいつくばっていると、ふっと視界に何かが入った。泉の周りを投げやりなステップで踊りまわっている者がいる。女神だ。
女神は頭や手足をバタバタと振り乱しながら、泥水を跳ね上げて躍っていた。いびつな円を描きながらクルクルと回り、彼女の周りに金色と銀色の水しぶきがキラキラ飛び散っていた。
私は毛布から這い出て、女神のもとへと走った。途中、何度かぬかるみに足を取られて地面に突っ伏しそうになる。彼女はこの不安定な足場の中、華麗に舞っている。笑っていた。悲しげに笑いながら、狂ったように何かを叫んでいる。私は彼女に向かって叫んだ。雨のドカドカ降る音が、なにもかもをかき消す。自分の叫び声さえ聴こえない豪雨が、私と女神の周りを白くつつみこんでいた。彼女のステップはだんだんキチガイじみていき、激しさを増すにつれて、ずぶ濡れになった彼女の金髪が宙を踊る。
「あなたが……落……は……金の……か? ……雨粒……か? あな……が……雨粒です……銀……あなた……落とした……あなた……落とした……落とした落としたおとしたおとしたオトシタオトシタ……シタ……落とした……キャハハ……ハハハ……ハハハ……オトシタオトシタおと……したオト……したオトシタおとしたおとしたおとし」
雨音に混じって、かすかに彼女の声が聴こえてくる。指先からは金色の雨粒と銀色の雨粒が、ボロボロと際限なくこぼれており、彼女がクルクルやるたびに、ギラっと輝く。今度の落とし主は、無数に雨粒を落とす、雨雲だった。
私は彼女に後ろから掴みかかり、耳元で叫んだ。やめろ。もうやめろ。その声が届いているのかいないのか。彼女は髪を振り乱しながらジタバタと抵抗し、物凄い力で私を地面にたたきつけた。もろに泥を被った顔で、彼女を見上げる。彼女は、私など意に介さぬように、あさっての方を向いて飛び跳ねている。気が狂っている。白いローブは濡れて肌にピッタリとくっつき、ローブの下から見える足首には、つぶつぶの泥がはりついていた。
私はよろけながら彼女のあとについていき、力の限り叫んだ。見ていられなかった。やめてくれ。すると、彼女は私のほうに向き直り、ぴたっと止まった。そして私に助けを請うような目をし、頭を抱え、涙とも雨ともつかぬもので顔をクシャクシャにしながら叫び返してきた。雨の音で何も聴こえなかった。彼女の唇は、物凄い速さで動き続ける。おそらく例のセリフを叫び続けているのだろう。
天から降りしきる全ての落し物に対応しようとしている、いや、させられている彼女の精神は、限界を迎えつつあるように見えた。私は女神をそっと抱きしめる。雨ですっかりと冷え切った彼女の体は、小刻みに震えていた。
「あなたが落としたのは……金の……雨粒ですか……それとも……?」
恨み言のような呟きが、私の胸を弱弱しく揺らした。私は女神の背中に手を回し、ゆっくりとさすった。彼女の手が、キュッと私の衣服を掴んだ。
夕方すぎになって、ようやく雨があがった。巨大樹の下、私は女神を抱きかかえながら、座って泉を見ていた。
この泉の女神のルールが、どんなものかは正確には分からない。無数に落ちた雨粒全てを処理するとしたら、女神は半永久的に雨の落とし主に語りかけねばならないところだったが、しばらくすると、彼女は私のもとから離れ、すっと立ち上がった。泣きはらした目は赤く腫れ、白い頬には幾重にも涙の筋が残っていた。少しやつれたようになった彼女は、ニコッとかすかに微笑むと、きびすを返し、泉に帰っていく。薄汚れた女神の後姿。足首や、白いローブには乾いた泥がこびりついている。足取りはよろよろとおぼつかず、相当に憔悴しているのが分かる。
女神は泉の前で立ち止まった。そして、ちらりと私のほうに振り返ると、控えめだが小さく手を振った。
彼女を助けたいと思った。好きだと思った。くだらないこの馬鹿げた泉を憎いと思った。泉にモノを落とす人も物も天も何もかもを消してやりたいと思った。糞みたいな人間の糞みたいな道徳を試すためだけに、得意げにこの忌まわしき呪いを考えた何者か、例えそれが神であったとしても許せなかった。こんな馬鹿な。モノを落とすなどという。それだけのことで。女神は! 四六時中! 何でもかんでも! 金銀に変えて! ……なんでもかんでも? 金銀に変えて? 何でも……? かんでも……? 何……でも! ああ! そうだ! 何でもいいのだ! そうだ! そうだったのだ。
私は力強く大地を蹴り、女神に向かって猛然と走り出した。女神は突進してくる私を見ても、眉一つ動かさず悲しげな微笑を浮かべている。速度を落とさないまま、私は女神に突き進んでいく。そして、女神の顔をジッと見つめながら、泉の前に立っている彼女を、思い切り突き飛ばした。
女神は穏やかな表情で、フワッと水上に投げ出され、泉に吸い込まれていった。背中、肩、胸、顔と順々にゆっくりと泉に入っていく女神の様子が、私の目に刻まれていく。
大げさな水しぶきがあがる。泉全体に波紋が伝わり、夕陽で赤く染まった泉がゆらゆらと揺れる。照り返しがギラギラと赤く、私は思わず目を細めた。一瞬の静寂。
やがて赤く揺れていた泉が、おとなしく凪いでくる。すると女神がゆっくりと泉の中央に浮かび上がってきた。いつものように、直立不動で水の上に立っている。その両腕には、金の女神と銀の女神が抱えられていた。女神はゆっくりとこちらに歩いてき、私の前で立ち止まると、言った。
「あなたが落としたのは、金の女神ですか? それとも銀の女神ですか?」
「いいえ、私が落としたのは、ただの女神です」
女神はにっこりと微笑んだ。
「あなたは正直者ですね。ご褒美に、金の女神と銀の女神。そして――」
彼女は私の胸に飛び込んで、そっとささやいた。
「私を差し上げましょう」
私と女神は長い口づけを交わし、その日から泉の女神はいなくなった。
↓ 人気ブログランキング。クリックで投票されます