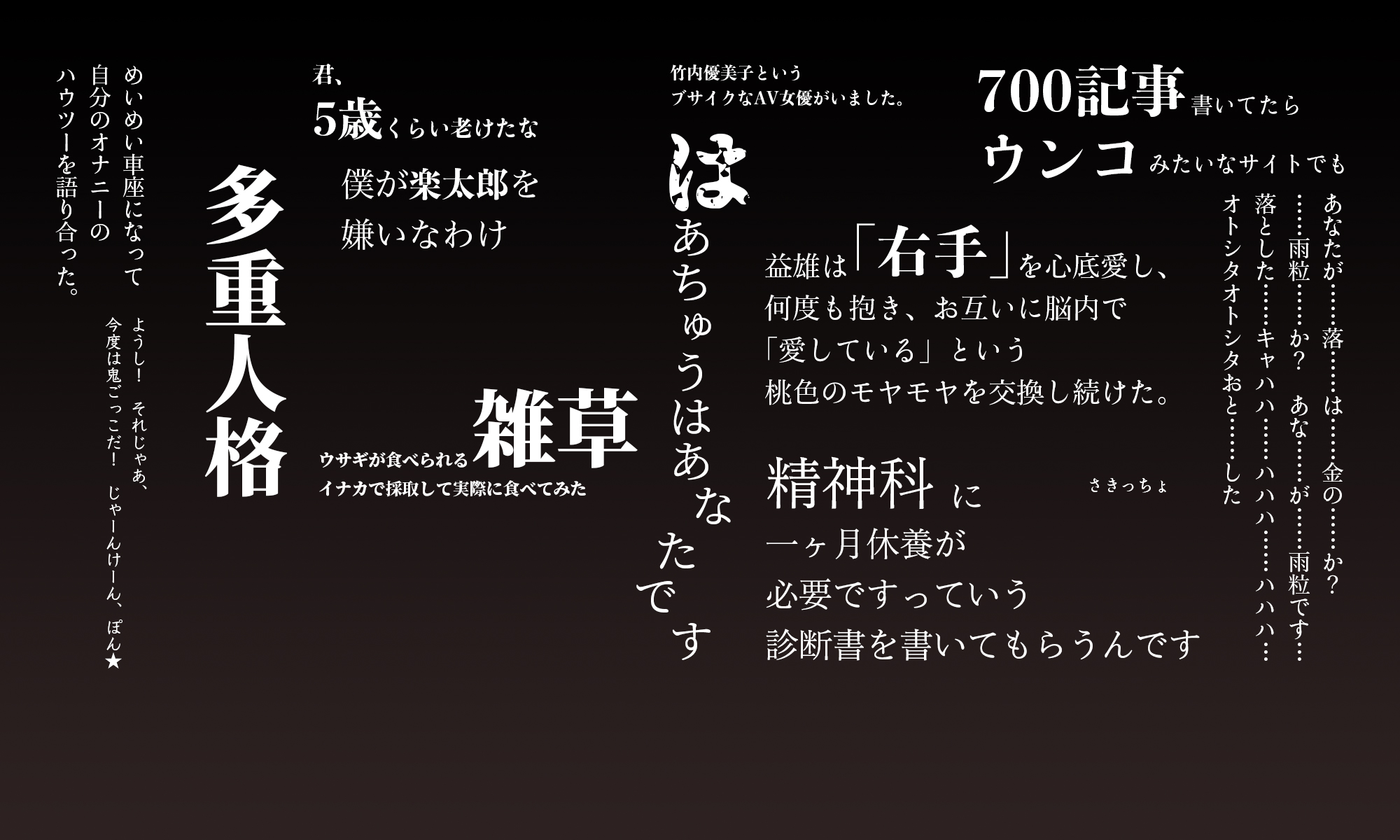だいたいムカついてるんですよ。ブログってもっとアレじゃない!? 気楽なものじゃなかった!? 便所の落書きみたいなさ。なんか最近価値つけようとしてない? 少しでも世の中の人にためになる情報を、ひいては世界をちょっとだけ良い方向に変えるんだ! みたいな肩肘張ったやつをさ! アフィリエイトだか情報商材をチラつかせながら、やれ地方はいいとか起業が云々とかさ! そういうの死ねよ! マジで死ねよ! 面白くないからどっか行っていいよ! みんなブログで情報収集しないから! 少なくとも俺はしないから! 意識高い系の君たちがあげてくる起業ノウハウやビジネス理論とか糞食らえだから。本買うから。紀伊国屋行って立ち読みして探すから! 帰っていいから。いや、じゃあ僕のブログは面白いかと言われれば別に面白くないよー! でも無価値だという点で君たちのブログと同じだねーうんここ☆
昨今のブログブームがあまりに金、金してる上、しかもそういう金、金してるやつに限って「ブログで稼いで何が悪いんですか? だって僕/私はこんなにコンテンツを提供してるんですよ」ってドヤ顔で言って、じゃあどういうコンテンツを提供しているかというと、漫画雑誌のレビューだとか、ひどい時は今日食べたご飯とかそんなもんゴミクズですやーん! それに金出してるの馬鹿しかいないじゃーん。馬鹿が金を誰かに払ってる様ってどう考えても不快じゃーん。
だから意趣返しとして、俺もゴミクズみたいなブログを発信してやります。反響があれば有料化しますのでお早めに読んでおくことをお勧めしますよー!(ゲペペー)
(ここからは有料記事となります糞食らえ)
「ザーメンで木製の椅子を溶かすたった一つの方法」
またまた中学の話だ。野球部の皆で会話している際に、
「どのようなやり方が良いか」
という話になった。当然のごとく効率的なノックの方法でも、栄養の摂り方でもなく、どのようなオナニーが最高かという話だ。めいめい車座になって自分のオナニーのハウツーを語り合った。床にこすりつけて行ういわゆる床ニーがあれば、オーソドックスなタイプの手コキ型のオナニー、少年の数だけオナニーのHOWがあった。そこには孔子式の答えが一つの教育ではなく、アメリカ式のみんなが答えを持っている的なオープンな空気が流れていた。どんなオナニーがあっても少年たちはお互いを尊重し、敬意を払って聞いていた。
そこにひときわ異彩を放つ回答をした者がいた。
「俺、椅子でするよ」
皆が「椅子!?」と振り向いた。皆の視線の先には彼がいた。
「椅子って、お前。どうやって?」
K君に顔射されそうになったキャプテンが血相を変える。彼は股に自分の右腕を挟んで
「椅子の脚があるじゃん。あれを股に挟んで登り棒でしこるときの要領でやるんよ」
登り棒でしこるという明確なイメージに、聞いていたメンバーは「あー」と合点がいった様子。これは女性にはわかるまいが男性には明白な表現である。「しかし椅子って」、「想像もつかない」などとメンバーがざわついている中、キャプテンが言った。
「なあ、今度見せてよ」
それにしてもこのキャプテンは人のオナニーを見過ぎなのであるが、兎にも角にもキャプテンが彼のうちにやってきた。母親が愛想よく麦茶などを出し、世間話に興じる。キャプテンはこんなキチガイなのになぜか彼の母親からの信頼が厚く、今日も野球についての真剣な議論がなされるのであろうと思っている。母親が去った後、おもむろに彼の学習机の椅子を見てキャプテンが口を開く。
「これか?」
キュルキュルキュルと音を立てながら、木製の学習椅子(スーパーマリオのキャラクターシールが付いている)を彼の眼の前に持ってくるキャプテン。
「で、どんな風にやるのよ」
彼は一旦そんきょの姿勢になると、そのまま椅子の脚の一つににじり寄り、キュッと股に脚を挟み込み上下に擦らせた。
「こんな感じ」
「え、そしたらズボン履いたままやるの?」
「いやズボンは脱ぐよ。脱いでこする」
「精子はどうするの?」
「そのままぶちまける」
青白くなったキャプテンが、バッとオナニーする脚(略してオナ脚)に目をやると、そこにはザーメンで腐食したオナ脚があった。木材を止めるネジは赤黒く完全に錆びつき、木が腐食して黒くブヨブヨに凹んでいる。
ぎゃあっと歓声とも嬌声とも言えない声が響き、誰彼ともなく椅子コールが始まった。
「イース! イース! イース! イース!」
その歓声の真っ只中に彼、いや、俺がいた。
まあなんというか、言い訳させてもらうと、オナニーに関しては早熟だった僕が編み出したのがこのオナニー方法で、小さい頃はズボンを履いたままやれるってんでお手軽だったのです。しかし、小4ぐらいかな? アレが出始めまして、そん時はオシッコかなあ、なんて思いながらやってたんですけど、まあそのうち気持ち悪くなってきて、パンツを脱いで直接こするやり方に変えていたわけです。んでそのままブチまけてティッシュで拭くという極めて合理的なやり方を堅守してたんですが、そこは人間の神秘。アルカリ性だか酸性のザー汁が椅子をじわじわと数年かけて侵食していて、中2の頃にはこうしててんやわんやの大騒ぎ。しばらく学校で「椅子」ってあだ名がつきましたからね。
そんでこう、久々に実家に帰った時にあの時の椅子がまだ置いてあるんですが、学習机の椅子ってすげえのな。一本、足が完全に腐ってるのに20年経った今でもまだ機能してて、懐かしさとともに感心する思いですね。
さて☆ どうだったでしょうか? 使わない7つの習慣並みに役立たない記事でしたが、これからも宜しくお願いします!!