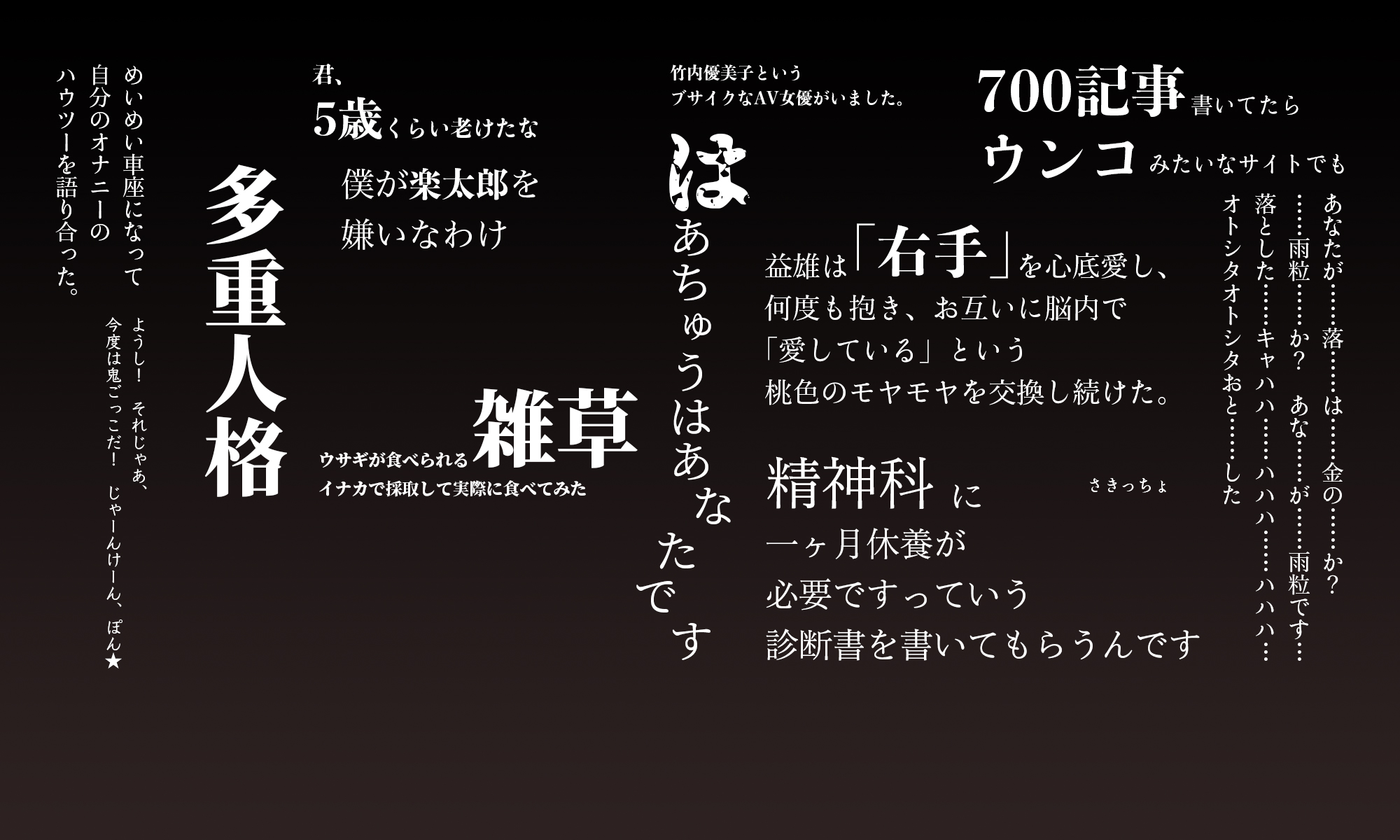シャイアンのぶん殴っても内定でないよブログ
その1 その2 その3
————————————————————————–
例えば誰か、立派な偉人の伝記を読んだとき。例えば誰か、立派な人の講演を聞いたとき。
俺は、「ようし、俺もやってやるぞ」と一念発起。
明日からは早起きをし、勉強をきちんとして、
ハキハキしゃべり、就活もバリバリし……と夢見るのだ。
だがその決心は、だいたい三日で挫折し、俺は
「人がそんなすぐに変われるわけがない」
と、半ば諦めの目つきで、もしくは悟ったようなフリをして自分を正当化する。
少しずつ変わっていくしかない。それは確かに正しいことなのだろうが、
俺は、その言葉を簡単に口にし、現実から逃げる。自分を成長させるのを拒む。
めんどくさかったり、他にしたいことがあったり、
大概は取るに足らない理由で、決心はもろくも崩れてしまう。
そんな自分の怠惰を憂い、心の中でグチグチと呪ったところで
なんの解決も見出せないことを俺は知っている。
努力のできない人間が上にのさばることなど絶対にできない。俺はそれを知っている。
だが知っているということがどれだけ俺の救いになるのだろう?
俺は知っているだけだ。物事をよく理解してるような顔をしながら、
頭の中だけで高尚な理論を振り回す。それだけだ。たったそれだけ。
ノベタを訪ねるのは、俺にとってなかなかに骨の折れることであった。
俺はノベタの家の前にたどり着くと、ある種の恐怖感でいっぱいになり、
呼び鈴が押せなくなる。
もしノベタがツネオやシスカちゃんのようになっていたら……
あの愚図でのろまのノベタまでもが、立派な就活生をやっていたとしたら。
俺はいよいよヤツを殴ってしまうかもしれない。
「殴ってしまうかもしれない」
俺が恐れているのは醜い自分であった。他人が成長し、それを素直に受け入れることもできず、
嫉妬の波に溺れるどうしようもない自分が恐ろしかった。
もし俺がノベタを殴ろうものなら……それは自分自身を、自分の心を殴るも同然の行為である。
俺はそれが怖かった。
ならばなぜノベタと会いたいと思ったのか? それはやはり……
そんなことを考えながら、ノベタの家の前でモジモジしていると、
唐突に2階の窓が開いた。
そこには懐かしい友人の顔――少なくとも俺はそう思っている――がある。懐かしいメガネ。
ノベタの家に上がると、ノベタはパジャマ姿で俺を迎え入れた。
顔にはもう何日も剃っていないと思われる無精ひげ。
顔もろくに洗っていないのか、なんとなくくすんだ色の肌をしている。
「シャイアンが来るなんて何年ぶりだろうね!」
嬉々として俺に話しかけるノベタの表情に、
「久しぶりの友と会う感慨」以外に感情は読み取れなかった。
純粋。こいつはいつでも純粋だ。他意がない。
喜色満面、無邪気に喋るノベタに案内されて、俺はヤツの部屋に入る。
部屋には湿った空気、それも人間の生活感を想起させるニオイをはらませた空気が充満していて、
少し圧迫感がある。
5畳ほどの部屋の中央に、ペチャンコの布団が鎮座していて、
布団の隅々には雑誌が散乱している。
部屋の一角には、ファイルと分厚い本とが乱雑に積まれていて、一つの山が形成されている。
枕元に開いてある雑誌には、「伊藤つばさスピード離婚!!」という見出しが書いてあった。
机には不均等かつ不安定につまれた本の山に、斜めにノートパソコンが開いてあり、
その後ろの窓から、まぶしいほど日光がさしこむ。が、部屋は仄暗いままだ。
俺は心の底から安堵を感じた。なあに、ダメ人間は俺だけじゃない。
ノベタはやはりノベタだ、案ずることはない。
そう考える俺がいて、意味のない安堵に身をゆだねる俺がいて、
一方で「だから何だ?」と問う俺もいた。
その問いは、俺にネットリとからみつき、心に不快な薄幕をはる。
とたんに息苦しくなる。
汚い部屋、堕落した自分、昔いじめられた友人。あらゆる事象を無視して、
ノベタはただただ喋り続けた。無邪気に、笑顔を絶やさず。まぶしいほどだ。
たまらなくなって俺は聞いた。
「お前、就活どうしてる?」
勢いよく喋り続けてきたノベタが、一瞬ぴたりとたじろぐ。
が、しかしたじろいだ時間は、気づかない者なら気づかないほど僅かで、
つまりはノベタは自然に振舞っているように見えた。
「やあ、全然ダメでね。でへへ」
そりゃダメだろうな。と思う自分を必死に抑える。
「シャイアンはどうなの?」
そう言うノベタの顔に、内定の出ていない者特有の卑屈さは感じられない。
いや、もしかしたら必死に顔に出るのを隠しているのかもしれない。
「まあ俺も、ダメだな。面接はけっこうしてるんだけど……」
嘘ではない。確かに面接はしているのだ。
「けっこう」と言えるのかは分からないけれど、確かに。
そう考えた後、俺はいったい誰に弁解しているのだ? と思う。
「たくさん面接受けてるの? うーん、すごいな。
僕はたまにしか受けらんないもん。なんか億劫でさ」
共感。俺は激しく共感した。めんどくさくて受けられない。
その意見をノベタから聞いて、俺は思わず笑いそうになる。
馬鹿にした笑いではない、仲間がいることを知った喜びの笑い。虚しい笑い。
ポツリポツリと就職の話をしたのち、俺達はどちらともなく話題を打ち切った。
それは双方とも就活がうまくいっていないことの証明のようで、
なんだか腹が立ったのだけれど(誰に対して?)、俺はノベタとの再会を楽しむことに決めた。
ノベタは、ツネオやシスカちゃんとは違い、堕落していて、享楽的。
他人に優しく、自分に甘く、やはり他人に甘かった。そう思えた。
俺は「だからこいつ、好きなんだよな。」と思った。(自分の仲間であることが)
俺達は、昔懐かしいバカ話をしながら、汚い部屋でテレビゲームをして遊んだ。
相変わらずノベタは下手くそで、俺は幾分か気まずい思いをしそうになったのだけれど、
ノベタは楽しそうにしていた。その楽しそうな顔を見て、安心するとともに、
俺達はこれでいいような気になってきた。
と、突然後ろのドアが開いた。
俺とノベタは、ビクッとして後ろを振り返ると、
満面の笑みを浮かべたおばさんが立っているのが見えた。
「あらタケシさん。ゆっくりしていって下さいね」
優しくそう言うと、おばさんは少しだけ荒々しい音を立てて、ドアを閉めた。
俺は見た。ニコニコ笑うおばさんの目の奥に、とてつもない怒りが混じっているのを見た。
それは怠惰な息子に対するものなのか、息子を遊ばせる原因になった
俺に対してなのかは分からない。
だが、おばさんの登場で、一気に俺達の楽しい空間はぶち壊された。それは確かだった。
テレビから聴こえる、派手な爆発の音や効果音だけが部屋に響き、
俺達は作り笑いを浮かべながら黙ってゲームに興じた。空気が重い。
就活という名の現実が途端に俺達の前に立ちふさがっていた。
いや、最初からあったはずだ。俺達はそれから目を背け、いっこうに前を見ようとしない。
ノベタは突然すっくと立ち上がると、ニコニコしながらこう言った。
「シャイアン、ヘルスにでも行こうか」
俺の心の中は、最早罪悪感でいっぱいであった。一刻も早く家に帰りたかった。
どう考えても、光の見えない道へと歩き出す俺達は、
しかしそれでもどうしようもなく寂しくて、歌舞伎町へと歩を進めるのである。
続く
——————————————————————————-
すいません、終わりませんでした。
↓ここをクリックするとランキングに投票されます(現在18位)

シャイアンのぶん殴っても内定でないよブログ その3 By Y平
~シャイアンのぶん殴っても内定でないよブログ~
その1 その2
-----------------------------------------------------------------------
大人になるとは一体どういうことなのか? なぜいつの間にか皆、大人になっていったのだろうか。
俺たちがガキのころ。ツネオは社長になりたがっていたし、
シスカちゃんは外交官になりたがっていた。
そして俺は、伊東つばさのような大物歌手になりたいと、夢見ていたのだ。
その夢は体が大きくなるにつれ、より現実的にしぼんでいき、ツネオはしがない会社員に。
シスカちゃんは訳のわからない金融あたりに勤め、そして誰かと結婚して
かつての夢は塵と消えていく。
最初は誰もが、「特別な存在になれる」と信じてやまない。
「大きなことができる」と信じてやまない。
だが、現実は漫画やドラマのようにスンナリとはいかず、
そんなヒーローみたいな存在になるためには、努力とか、忍耐だとか、
そして何より運だとかが重要になってくる。
誰しもがその道程で挫折し、あるいは妥協し、
社会の歯車として四苦八苦しながら働き、身を削っていく。
そこにはスリリングなやりとりは滅多になければ、
英雄とあがめたてられるような事件なんてほとんど、ない。
そうして長年身を削って生きてきたあと、死ぬ間際になって、
「ああ、俺はいい人生を送ったよ……な?」などと、
自分に言い聞かせ、自己満足のうちに人は死んでいくのではないか?
武道館をいっぱいにすることもなく。ミリオンセラーを出すこともなく。
自家用機を購入することもなく。
そんな生き方を「夢がない」と一蹴してしまう者が子供で、
その中にも生きがいを見出せる者が大人なのだろうか?
俺は「夢がない」と思ってしまう。多くの人間が歩むような道なんて、
歩みたくないと思っている。
しかしそれでは、俺は歌手になるための努力をしてきたかというと、「?」である。
ただただ、大声で近所に騒音を撒き散らし、自分の欠点を省みろうともせず、
才能があると半ば自己暗示をかけ、気分がのったときにだけ歌い、
そして皆は俺の音痴さを煙たがった。
中学になって俺は思った。「才能がない」と。しかしそれは逃げである。
「才能がない」というもっともらしい理由をつけて、俺は逃げたのだ。
あのときならば、まだ道はあった。いくらでも道はあった。
本気になれば、できないことはなかった……はずである。
それは何も、俺だけではなくて、シスカちゃんも、ツネオも……そしてノベタも。
掃除機の音で目を覚ました俺は、あかない瞼をこすりながらゆっくりと起き上がる。
枕もとの時計をフッと見やると、時計は既に8時半を指している。
朝日が秋とは思えない鋭い強さで、俺の布団に差し込んでいた。
ジンワリとパジャマが湿っていて、室内は暖かいというよりは暑いくらいである。
ずおーっという、掃除機の音を聞きながら俺は部屋を出る。正面には妹のシャイ子の部屋。
この暑さのなか、襖は締め切られており、中にはシャイ子が熱心にマンガを書いている気配がする。
こんなに朝早くから、精の出ることだ。
ギシギシと古びた階段を降りると、母ちゃんが掃除機をかけているのが見える。
母ちゃんは廊下にぼおっとつったている俺を発見すると、朝もはよからがなり声で喚く。
「いつまで寝てんだい! さっさと家の手伝いするか、大学にでも行きな!」
大学は休みなのだが、弁解するのもめんどくさかったので、適当に生返事して俺は店先に向かった。
俺達の家庭は、自営業で生計を立てている。
昔は地域に密着した乾物屋で、なかなか繁盛していたのだが、
向かいに大きなスーパーマーケットができて以来、客足はグンと遠のいたままだ。
閉められたシャッターを内側から開けると、一気に店内が明るくなった。
正面に見える太陽が、ぎらぎらと俺を照らし、思わず手をかかげ、目を細める。
振り返ると、たくさんの干物が入ったビンのわきに、小さなざるがかかっているのが見える。
ざるの中に入っている小銭は、随分前から179円のままだ。
途端にツネオが羨ましくなる。
俺はビンに入っている干物を適当につまむと、干物を口に入れたまま身支度を整える。
冷蔵庫からパック牛乳を取り出し、そのままラッパ飲みする。
「大学行ってくる」
俺は母ちゃんに向かって叫ぶと、そのまま店先から家を出た。母ちゃんは返事もしなかった。
もちろん、大学へ行く気など毛頭ない。ただそこらをブラッと散歩したかっただけだ。
ブラッとして、空き地の土管の上で寝るのである。
俺は朝の幾分か強い日差しの中、自転車も使わずこつこつと歩き、空き地へとたどり着いた。
有刺鉄線を乗り越え、積まれている土管の上へ腰を下ろす。
そこでボオッと青い空を眺めるに徹した。
思えばなぜ大学などに入ったのだろう。
中学の頃、成績の悪かった俺は3流の私立高校へと進学した。
そこではまるで勉強もせず、大好きな野球ばかりをやるのだが、俺は楽しかったし満足していた。
甲子園へ行くことこそできなかったが、三年の夏、二番手ピッチャーとして夏の大会に出場。
結果は、三回戦で押し出しのサヨナラ四球を出し、
失意のまま引退することとなったのだが、俺の心は晴れ晴れとしていた。
野球の感傷に浸りながら、俺がゆるゆると高校へ通っている秋。
世間一般の高校生はすべて、受験か就職かという人生の岐路へと立たされていた。
俺達の学校は、進学校ではなかったのだが、それでも全校の2パーセントぐらいは
大学へ進もうとするものもいた。
進学組は、就職組とは違って、授業にはあまり出ない。
予備校やら、自宅学習やら、はたまた高校の進学担当の教師の特別補習などを受け、
就職組とは物理的に隔絶される。
そして毎年何名かは、二流の私立、三流の私立に見事合格し、
就職組とは少し違った生活を送ることになるのだ。
その進学組の中に、あのノベタがいたのである。
飄々とした風貌のノベタが、冴えない顔して特別補習を受けているのを見たとき、
俺は言いようもない劣等感にさいなまれた。
無論、ノベタが俺より下であることは確たるものとして、俺の心の内を支配しているのだけれど
(そんな汚いことを考える自分に嫌悪感を覚え始めたのもこのころ)、
ノベタに対して嫌悪を……憎しみを抱いた。
「ノベタのくせに生意気だぞ」
俺はノベタに向かってそう言い放つと、その日中に担任のところに行き、
進学組に加えてもらった。ノベタは意外な仲間が増えたことに、純粋に喜んでいるようだったが、
俺の思惑は違う。ただノベタが生意気だったから。
動機不純ではあるが、そのときの俺は確かにノベタのためだけに大学進学を選んだ。
そうして今、俺は大学に通っている。そしてまた人生の岐路に立たされ行動できないでいる。
理想も何もなく、入れてくれる企業に苦もなく入る。
転職する行動力もない俺は、そこで待遇悪く働かされ、一生を終えてしまうのか。
そんな人生は……
ノベタに会いたい。俺は急にノベタに会いたくなった。
確か最後に会ったのは成人式のときだった。一体やつはどうしているのだろう?
相変わらずノベタらしく、不器用に生きているのだろうか。
それともツネオやシスカちゃんのように、はつらつと、元気にやっているのだろうか。
就活の話をイキイキと話すノベタを想像すると、ざわざわと心が乱されていく。
ノベタノクセニ
心の底からの声なき声が、俺の内部を響き渡らせる。
そして俺はその音響に、怒りに、心身を任せつつありながらも、
心の底では自分が墜ちていくのを認識していた。このままじゃいけない。
俺は土管から飛び降りると、空き地を出、まっすぐにノベタの家に向かって歩き出した。
デキの悪いあいつが、どう生きているか。デキの悪い俺が、どう生きるべきか。
確かめようと思ったのだ。
少ししめった秋風が空き地をざわっと撫でる。
雨に濡れた草木の匂いが、彼の去った後に離散していった。
~最終話に続く~
↓ここをクリックするとランキングに投票されます(現在22位)

----------------------------------------------------------------------------
● オフレコ ~作者の叫び~ ●
目下の話題は日ハムだろうがよおおおおおおおお!!
なんで俺はこんなもん書いてるんだよおおおお!!! SHINJO!!
シャイアンのぶん殴っても内定でないよブログ その2 By Y平
~シャイアンのぶん殴っても内定でないよブログ~
その1
----------------------------------------------------------------------
駅を出たやや狭い商店街の路地に、赤々としたスポーツカーが止まる。
どこかの中華飯店のまとわりつくような油のニオイのなかで、
その深紅のスポーツカーが微妙にマッチしているように見えるのは、下品さからだろうか。
そしてまた、車上でやらしい笑みを浮かべているイヤに前髪の長い男も、
根っからに染みついた下品さがその油のニオイにフィットする。
花柄のシャツに、タイトなジーンズ。浅黒いサングラスが個々で下品さを増長してみせる。
髪が黒く、ピアスの穴が赤い点々になって塞がれていることが、
彼が就活中であるという体裁をかろうじて保っている。
「ツネオ……か?」
俺は車の上で、ヘラヘラとこちらを見ている男に喋りかけた。
「やあ、シャイアン! 元気ぃー?」
昔からツネオの喋り方が気に食わなかった。あいつの話し方は、
ときどき人を食ったような調子になることがある。
例えば俺がバカなことを言っちまったとき、
あいつは決まって「ウシャシャシャシャ」とどっかの大物漫画家特有の変な笑い声をあげた。
その度に、俺は「ドガア!」と意味不明な咆哮をあげ、ツネオをギタギタに殴ってやったものだ。
今も非常にむかついた――特に語尾が――のだが、
拳をぎゅっと握る以外俺にやれることはなかった。
人を殴るには、俺達は大人になりすぎた。
気がつくと、俺はツネオに家まで送ってもらうことになっていた。
ツネオは俺を助手席に乗せると、すばやく発進する。
人と自転車と、そしてゴミとが一体となった商店街を、
やや速いスピードでするすると通り抜けていく。
途中で乳母車を押すお婆さんにサイドミラーが当たりそうになったが、
ツネオは別段動揺している様子もない。抜き去ったお婆さんを見ると、
お婆さんもまたマイペースに乳母車を押している。
ツネオは薄ら笑いを浮かべながら、髪をそよがせ黙っている。俺はなんとなく落ち着かなかった。
「ツネオ、はええよ」
「だーいじょぶだいじょぶ、大したことないって」
俺はまた拳をぎゅうっと握った。
視界の開けた交差点に出る。あたりはすっかり真っ暗になっていて、
俺の目に、前方で信号待ちしている車の群れからライトが入ってくる。
ツネオはしばらく無言で前を向いていたが、
急に左折の方向指示器を出すと――俺の家は右だ――早口に喋った。
「ちょっとドライブしてこうか」
「遠慮しとく」と答えようとしたとき既に、ツネオの車は左折を始めていた。
俺は小さく吐息のような声を出すだけで、次の言葉がつなげられない。
ツネオは俺が喋り始めると思って少し黙るが、実際には俺は喋らなかった。
変な会話の間が、ギクシャクとしたムードを更にかきたてる。
しかしツネオは相変わらず薄ら笑いを浮かべ、気持ちよさそうに運転しているようだ。
何がなんだか分からなくなる。
「シャイアンさー」
来た。と思った。次に出る言葉は分かっている。
それは大学四年生である俺達が、もっとも会話を広げやすい話題。
腐るほど同じようなことを聞かされるが、不思議と皆はイキイキしたり、
あるいは「俺もやらねば」とモテベイティブになってみたりするあのテーマ。
どいつもこいつも一緒だ。ツネオの顔に少し真面目な雰囲気が漂う。
俺は先に聞かれるよりはむしろ、先手を打ったほうが得策だと思い、
ツネオの声に自分の声をかぶせる。
「お前、就活どう?」
刹那、ツネオの顔に少しだけ不快感が写ったが、すぐに消え、またニヤニヤしだす。
「いやあ、僕は全然だめだね」
謙遜があっても俺は油断しない。皆が皆で謙遜するくせに、
俺が弱音を吐くと全力で非難することを知っているからだ。
「私はあんたのために言ってるんだ、あんたは前を向いていかなきゃならないんだ。」
そんな言葉を顔中に塗りたくり、俺を全力で批判してくる同級生達。
しまいには、「お前はほんとダメなヤツだな……」と呆れた目で、
哀れな者を見るような目で俺を見下す同級生達。
そんな同級生達と同じ性質を、ツネオが持っていないとは限らない。
いやおそらくこういう人種は持っていることだろう。
人より上に立ちたがる心、人を見下す心。
「なーに言ってんだ。お前なんか親父さんのコネですぐに決まんだろ?」
できるだけ軽い調子でそう切り出す。俺は僻みの心を極力隠すようにして、
あえて快活にふるまう。俺の問いかけを受けても、相変わらずツネオの顔はヘラヘラしている。
「決まらないんだなこれが。就活舐めてたよ」
少しだけツネオの顔に影ができたように感じる。
「どうして? お前の親父、社長だろうが。親父さんに頼めば一発なんだろ?」
自分でも馬鹿なこと言ってるなと思う。俺はさらに拳を握り締める。
「そりゃあ、まあそうなんだけど」
「なんでえなんでえ! 会社でも潰れたのか? ハハハハハ」
ツネオは少しだけ噴出すると、スッと俺のほうに顔を向け、笑って見せた。
「まさか! パパの会社は潰れないよ」
「ならどうして」
ツネオはその問いかけに、一瞬逡巡の表情を浮かべたが、
すぐにまたヘラヘラしながら続ける。
「僕が……コネを使わないって決めたんだ」
ツネオは、少しだけ真面目くさってそういった。
だが、気取ってる風ではなく極めて自然体に真面目ぶって見せた。
「僕、さ。昔から裕福に……っつったら嫌味ったらしいけど、まあ実際そうだ。
裕福に育ってきちゃったから、全然苦労を知らなくて。
おまけに勉強もそんなにできるわけじゃないし、なんもいいとこないじゃん?」
ツネオがあまりにツネオらしくないことを喋るので、俺はあっけにとられていた。
何か返事をしなければとも思うが、もう少しツネオに喋らせてやることにした。
「大学に入って、色々勉強して……思ったんだ。僕って全然ダメだなって。ウヒヒヒ」
笑い方こそツネオのそれであったが、こんな弱気な……いや弱気ではないな、
現実的なツネオを見るのは初めてだった。
「研究室に入って、いろんな奴らと会って……あと、インターンもした。
世の中にはすごいやつがいっぱいいるなと思ったよ。
今の僕じゃあ、パパの会社に行ったってどうにもならないなあってさ」
調子よく走っている車の少し前方で、信号が赤に変わった。
少し強引なブレーキングで、二人の体はがくっと前に出る。
車が止まって、ツネオの声がよく聞こえるようになった。
「だから僕は、パパの会社以外でまずは就職しようと思ったんだ。
なあに、今の僕じゃあ失敗するけどさ。どんどん失敗してどんどん学んでいこうと思ったわけ。
ウヒヒ、といってもまだ内定は出てないんだけどね。
明日も面接、あさっても面接。エントリーシート書くの、
やったらうまくなっちゃってさ。ヒャハ」
信号機が青に変わる。スネオはちいさく「おっと」と声を出すと、
車は再びゆっくりと加速し始める。
俺は思考が止まっていた。既にツネオの声は耳に入ってるようで入っていなかった。
意味は理解できるが、それ以上に思考はどんどん停止しよう停止しようと努力しているように思えた。
ツネオがこんなことを考えているなんて、信じたくなかった。
「じゃあ、シャイアン。ここでいいかい?」
「ああ、ありがとう。助かったぜ」
ツネオは街路樹の下で車をゆっくりと止める。
俺はドアを下の縁石にすらないように注意を払いながら、ゆっくりとドアを開け車外へ出る。
「じゃあシャイアン。またね。」
「おお、今度はお互い内定が決まったときに会おうぜ」
「うん。でも僕、明日にでも決まっちゃうかもしれないよ?」
「ふふ、どーだかな」
「なんたって面接はハンサムのが有利」
「言ってろ、ばーか」
下品な笑い声をあげるとそのままツネオは荒々しくアクセルを踏み込み、
スポーツカーを発進させる。
ハザードを少し点けて俺に挨拶すると、そのまま夜の車の波に消えていった。
ツネオが行った先を見ると、信号機だとか、車の尾灯だとか、
光という光があちこちで夜を彩っているのが見える。
幻みたいにみんなぼやけているのが、けっこう綺麗だった。
ツネオはコネで楽に内定取るものだと思っていた。
なのに今のツネオは自分の力で就活し、そして未だに辛酸を舐め続けている。
秋採用ですら決まりだしているこの時期に、だ。
ツネオがコネを使って内定を取ったとしても、やはり俺としては腹が立つが、
逆に頑張っているツネオにも腹が立った。
落とされるという屈辱に耐え、自分を磨くために動いているツネオに腹が立つ。
ヤツらしくない。なんで人はそうまで変わろうとするんだ。
なんでそんなにみんな……大人なんだ。
俺は下を向きながら歩きだした。カバンがひどく重たかった。
~その3に続く~
↓ここをクリックするとランキングに投票されます(現在19位)

シャイアンのぶん殴っても内定でないよブログ その1 By Y平
プルルルルルルルルルルル。
「まもなく三番線から電車が発車します。黄色い線までお下がりください。」
ピーヒロヒィ!
どこか間抜けな笛が駅のホームに鳴り響く。
俺は、扉まで全速力で走りきると、満員の西部線に強引にでかい体を押し沈めた。
前のOLにギュウと体を押し付け、扉に挟まれないようにがんばる。
ぶしゅう。
どこからともなく空気の抜けたような音が鳴り、扉が体すれすれを滑り閉じていく。
バタン。
扉が閉められると、途端に満員電車特有のニオイ――人間の脂や汗のニオイ、
香水やら呼吸のニオイやら――がジンワリと鼻孔に侵入してくる。
車内は生暖かい空気が充満しており、不快。左のオヤジのハゲ頭には、
無数の汗の粒がプツプツと浮き出ているのが分かる。そしてもちろん、
俺の顔もまた汗で湿っており、就活用に短く刈り込んだもみ上げに汗が
たらりと滑っていくのが感じられる。
息が苦しい。ちくしょう、走るんじゃなかった。急ぐ用などどこにもないはずなのに。
今日はとある二流企業の一次面接であった。
出来杉を脅して書かせたエントリーシート(当然俺の)が奇跡的に通り、
就活始めて以来通算二回目の面接があったのだ。
就活が始まった当初は、俺様のエントリーシートを通さないなんて何事、
そんな企業こっちから願い下げだっつーの! などと息巻いていた俺だったが、
そのときから俺は自分の力不足に気づいていた。企業から見たら、論理的思考もできない、
おまけに自分の意見をこぶし以外で伝えるすべを知らない俺などに、
魅力を感じようだなんて思うまい。それは俺も気づいていた。
案の定、俺は面接官の最初の質問、
「なぜわが社を志望したのですか?」というベーシックな質問に、答えることができなかった。
どもるばかりで、ついて出てくる言葉は断片的。
うまく答えねばと焦れば焦るほど、無造作な言葉が勝手に口から溢れ、
テーマを盛り上げることなく萎んでいく。
終いには「もうけっこうです。ありがとうございました」などと、
機械的笑みを浮かべた面接官に半ば強引に打ち切られてしまった。
作り笑いがひどくむかついた……はずだったが、不思議と怒りの感情は沸き起こらない。
ただただ俺は沈んでいったのだった。
その帰り道がこの満員電車だ。人がギュウギュウにつめられた車内で、俺は微動だにできない。
前のOLと左右のサラリーマンにつめられ、足場が爪先立ちするしかないほど狭まっている。
ムンムンとした空気に湿らされた窓に背中が押し付けられてイヤだ。
おまけに俺の鼻の先5センチには前のOLの頭がある。
セミロングの髪は黒々と輝いていて、艶やかだったが、
俺はその髪を鼻に吸い込んでしまうような気がして、若干呼吸を弱める。
それが余計に苦しくて、汗はとめどなく溢れてきて、段々イライラした気分になっていく。
就活のイライラも手伝って、鋭い目でその女のつむじを見ていると、
女はフッと首を動かして、こちらを横目で見た。
鼻息が髪にあたるだとか、理不尽な文句をつけられそうな気がして、
俺はすばやく目線を中つり広告に移す。
こういう小さい自分がイヤだったが、そんな感情はすぐに打ち消された。
「タケシさん?」
顔のすぐ下から、聞き覚えのある声が聞こえてくる。
目線を下げると、俺の胸の辺りにピットリとくっついたシスカちゃんの顔があった。
ずっとOLと思っていたのだが、なるほど。よく見ると、
シスカちゃんはリクルートスーツを着ているようだ。
「シスカちゃんか」
同級生のシスカちゃんがいた。小学生の頃よりだいぶ大人びていたが、
大きな目と形のいいマツゲ、
小さな鼻に、モチモチした肌は、俺の頭に瞬時にシスカちゃんを連想させた。
昔のクラスのアイドルに会い、俺の心は踊りに踊った。
が、すぐに「まいったな」とも思ってしまうのである。
「久しぶり? 元気そうね。」
俺は、ああとか、おうとか。生返事を返しながら、気分が滅入っていくのが分かる。
そもそも小学生の頃から、シスカちゃんとは喋っていそうであまり喋っていない。
シスカちゃんと話すとき、たいていツネオやノベタが一緒であることが多かったのだが、
今考えると二人きりで喋ったことなど一度もない。
シスカちゃんに憧れる気持ちを持つ一方で、なんとなく可愛い女子と一緒になることが怖かった。
ツネオやノベタなら俺が好き勝手喋っていればよかった。
奴らは俺に対して文句があっても何も言わないし、ガタガタ抜かせばぶん殴ってしまえばいい。
しかしシスカちゃんはそうはいかない。シスカちゃんに気を使わせることなど、
いくら傲慢な俺とて穏やかではないのだ。
一度ノベタたちと白亜紀の恐竜時代に大旅行をしたことがあったが、
そのときも俺はツネオの側にずっとおり、なるべくシスカちゃんと二人になることは避けた。
そんなわけで、俺がそういう態度を取っているのを暗黙のうちにシスカちゃんは気づいていた。
なので今日までシスカちゃんは俺とは極力話さないように勤めていると思ってきたのだが、
目の前のシスカちゃんは……何か様子がおかしい。
「今、卒業研究と就活がかぶっててね、たーいへんなの。
バイトもしなくちゃなんないし……あ、バイトはウェイトレスやってるんだけどね。
そこのお客さんがなんか、ふふ……言っちゃだめだけどタチが悪くって。
対応に困っちゃうのよね。でもそういう対応するのって実はタメになっちゃってて。
やっぱり赤の他人といきなりコミュニケーションとるのって大切で――」
よく喋る。かつてシスカちゃんは俺にこんなに喋っていただろうか。
その場を取り繕うために無理に会話を搾り出す。
俺の知っているシスカちゃんはそんなことをやるような女ではなかった。
シスカちゃんの会話はいつも何らかの重みがあり、優しさがあり、そして媚びがなかった。
なのにこのシスカちゃんは、何か女子大生の枠に収まった、
いや、就活生らしいイキイキした口調であった。
快活で明朗だったが、シスカちゃんらしさは大分失われてしまったように思われる。
「今日は最終面接だったのよ。タケシさんは、就活、どう?」
出ると思った。猫も杓子も就活就活。それ以外に会話はないってのか。
シスカちゃんまでもが、就活生という枠に捕えられてしまったようで、
俺はひどく不快になった。なぜ不快になったのだろう?
その理由は、自分もそうなるべきであることが分かっているからであった。
ハキハキと、明確に、魅力的に、細かに、簡潔に自分を伝える。
それが今の俺には明らかに不足していたし、何より必要であった。
今のちょっとした会話でシスカちゃんはそれをできるだろうことが分かった。
羨ましい気持ちより、腹だたしい気持ちが勝ってしまいそうになる。
「まあ、ぼちぼちよ」
そして俺はシスカちゃんを見極めるために、さぐるように次の言葉を繰り出したのだ。
「最終面接ってすごいね。さすがシスカちゃん」
シスカちゃんは、待ってましたとばかりに顔を輝かせた。
ギュウギュウの車内の中で、シスカちゃんだけがイキイキとしている。
「第一志望じゃないんだけどね。でも練習のつもりで……っていっても結構ちゃんとした企業なんだけど……」
聞いてないテーマまでも率先して進めていく。
ここからは自分の武勇伝に移るのだろう。どいつもこいつもおんなじよ。
「OG訪問した企業だったのね。んで、よさそうな社風だったから、
何事も経験だし受けてみようかなって。」
「OG訪問だって? すごいなあシスカちゃんは。」
「すごくないわよぉ。私の場合自己分析をちゃんとして早くから自分の方向性が見えたから……
やっぱり行きたい方面の企業だと、第一志望じゃなくても本気になれるわよね。」
「自己分析かあ……あはは。俺、全然やってないや」
精一杯おどけてこの言葉を吐き出してみる。途端にシスカちゃんの顔が曇る。
まあ分かっていたことだけど。
「こんなこと言うとあれだけど……タケシさん、ちゃんと自己分析はしたほうがいいわよ。
自己啓発になるし、自分に向いている分野、向いてない分野をはっきりしたほうが、就活に絶対便利だから。」
俺は予想通りの言葉をシスカちゃんが言うのを、怒りを抑えながら聞いていた。
そしてまたおどけてこう言った。
「でも今更……俺……自己分析なんてやったって、しゃーないよ。」
「それがいけないの。たとえ就活につながらなくたって、
何かの役に立つから。それにまだ秋採用の時期じゃない。
がんばればきっと。でも頑張るといっても闇雲に頑張っても意味ないの、例えば……」
それからシスカちゃんは俺が電車を降りるまで、どこかで聞いたような就活話を長々とした。
シスカちゃんの話し方は、数々の面接をくぐってきたプロの話し方で、
それは自信と……なにより自己陶酔で満ちた話し方であった。
一種の就活ナルチシズム。私、しっかりしてるでしょ? えらいでしょ?
というセリフが聞こえてきそうな物言いが腹だたしい。
たとえそのアドバイスが100%正しくても、俺には許せなかった。
むしろシスカちゃんの非のなさが腹立たしかったのだ。
俺が電車を降りるとき、シスカちゃんは言った。
「力をおとさないで。がんばればきっといつかなんとかなるのよ。」
一度も俺が就活で苦戦したなんて言ってないのだが、
会話の流れでそういうことになってしまったようだ。
あっているのが余計に……俺の胸をかきむしった。同情するな。そんなことは分かってる。
俺はズボンのポケットから定期入れを荒々しく引っつかむと、
人がパラパラと出入りするプラットホームを早足で歩いていく。
後ろから、くたびれたスーツを着たサラリーマンが、背中を丸めながら無表情で通り過ぎる。
空を見上げると、灰色の雲が重く俺にのしかかってくるような気がした。
プラットホームの外灯がそこだけ妙にボウッと光っていて、
それ以外のところでは既に闇が侵入しつつある。
風が寒くなってきた。定期券を自動改札機に入れ損ね時間を食う。
後ろの人が舌打ちしたような気がした。
俺は駅を出ると、正面の狭い道に広がる商店街の光を眺める。
左右のゴチャゴチャ光る建物のあちこちから看板が顔を出しているのが見える。
車の通る音をベースに、人の話し声や、店のBGMが主旋律を奏で、
商店街そのものが音楽のようである。
さっきのサラリーマンはもうどこにもいない。
数分前にはシスカちゃんと話していた自分は今ひとりぼっちだ。
人がたくさんいる。多人数で笑っている人もいれば、
無表情に一人、下を向きながら歩を進める人もいる。
(俺は果たして就職したいのだろうか……)
そんなことを一人ボウッと考えていると、俺の前に、左ハンドルのオープンカーがゆっくりと停止した。
そこには見慣れた顔が生えているような気がした。
「シャイアンじゃない?」
俺は声に反応して、その見慣れた顔を凝視する。
~その2に続く~
↓ここをクリックするとランキングに投票されます(現在20位)

----------------------------------------------------------------------—-
出木杉 ≠ 出来過